社会人1年目、孤独と不安の中で出会った「お金の本」
私はもともと貯金や資産運用といった分野に興味を持っていた。入社後最初の配属は、発電所の三交代勤務であった。「社外に活路を見出した配属1年目 〜孤独と配属ガチャの現実〜」でも書いたように、当時は同じ班の人たちと業務外で交流する機会もほとんどなく、基本的には家と職場を往復する日々であった。
変則勤務のため、勤務時間外は一人で過ごす時間も多く、その時間を使って読書することが自然と習慣になった。中でも夢中になって読んだのは、お金や資産運用に関する本だった。投資、株、税金――とりわけ社会人になってから、給与から引かれる税金(社会保険料含む)に驚き、税への関心が強くなっていった。特に2年目に住民税が課せられたときは、さらに大きな衝撃を受けた。税金に興味があるというのは、世間的には少々変わっているのかもしれない。
しかし、当時は『金持ち父さん、貧乏父さん』(ロバート・キヨサキ著)などのお金に関する本も話題となっており、「経済的自由」という言葉にも惹かれるようになった。学生時代は論文以外ほとんど読まなかった私が、社会人になってから本を手に取るとは思ってもいなかった。
「安定企業」でも将来は不安──就職氷河期という時代背景
私が就職したのは、いわゆる「就職氷河期」と呼ばれる時期である。公務員以外の将来は不透明であり、「安定」と言われる電力会社に就職しても、どこか不安を感じていた。実際、私が入社した当時から「電力自由化」の話題が新入社員研修でも頻繁に取り上げられており、電力業界にもいずれ競争の波が押し寄せると予想されていた。(事実、東日本大震災以降、電力業界は本格的な自由化へ移行した。)
さらに、私自身ASD・ADHDの傾向があり、研修や配属された三交代勤務の班の中でも自然に輪に入ることが難しく、孤立感を覚える場面が多かった。組織の中でうまくやっていけるのかという不安は常にあった。
そうした状況の中、「自分の生活は自分で守るしかない」という意識が高まり、資産運用への関心が一段と深まっていった。
お金があれば心が安定するという発見
当時の私は、極端な考え方かもしれないが「300万円あれば、リストラされても2年は耐えられる」といったことを真剣に考えていた。毎月の貯金額が増えていくのが嬉しく、その数字を見ることが小さな楽しみになっていた。
就職氷河期で生活に困っている人の話や、リストラのニュースを目にするたびに、「いつ自分がそうなってもおかしくない」と感じていた。そんな不安があったからこそ、会社に頼らない経済的自由という考え方に強く惹かれていったのだと思う。
発達グレーと資産運用の相性の良さ
ASD・ADHD、吃音といった発達障害の傾向がある人にとって、資産運用は非常に相性が良いと感じている。興味のある分野にはとことん没頭でき、地道な作業の繰り返しも苦にならない。これはまさに、投資や株式分析といった分野において強みになる特性である。
興味のある企業の株式を徹底的に調べ、資産運用関連の書籍を次々に読み込んでいく。これらはすべて一人で完結でき、上司への確認も同僚との調整も必要ない。そのため、コミュニケーションや会話が苦手な私でもストレスを感じることなく取り組める。
資産運用のおかげで得られた心の余裕
事実、約20年資産運用を続けてきた結果、それなりの資産を築くことができた。もちろん失敗もあったが、継続してきてよかったと心から思っている。
職場で嫌なことがあった日でも、昇進が見送られても、配当金が振り込まれるだけで気持ちが少し楽になる。「給与以外の収入源を持つ」ということが、精神的な支えになるのだ。
現在も私は資産運用を続けているが、今や目的は「生活防衛」ではなく「会社への依存度を下げること」である。配当収入が増え、ローン返済のスピードも上がることで、自由が一歩ずつ近づいていると実感している。
たとえ仕事でミスをして叱責されても、「自分には他にも収入源がある」と思えるだけで、心に余裕が生まれる。この感覚は、資産運用を始めなければ得られなかったものである。
終わりに──会社だけが人生ではない
ASD・ADHDや吃音の傾向があり、会社での立ち回りに悩む人は少なくないと思う。私自身、そうした一人であるが、資産運用という「もう一つの柱」を持つことで、生き方に幅が出たと実感している。
「給与だけに頼らない生き方」「自分の興味を武器にする資産運用」。これらは、発達グレーな自分にとって、これからも、自分らしく生きるための大切な習慣として続けていきたい。


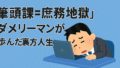
コメント