仕事中に起きるケアレスミスについて、私なりに原因と対策を考えてみた。その結果「集中の中断」ではないかと感じている。「集中の中断」が繰り返されることで想像以上に頭が疲れるのだと思う。
集中が途切れるとき、ミスが生まれる
私の場合、作業中、ほんの些細なことで集中が切れてしまう。たとえば、電話が鳴ったり、誰かに声をかけられたりするだけで考えていたことがリセットされてしまう。
特に集中が中断され困るのは以下のような場面である。
- アイディアを練っている最中
- 資料やメールの文案を考えている最中
- 計算や細かい確認作業をしている最中
これらのタイミングで話しかけられると、直前までの思考がすっかり抜け落ちてしまい、再び元の作業に戻るまでに多くの時間を要する。
その結果、誤字脱字や不自然な文章、数値の転記ミスなどが発生してしまう。
特に「集中⇒中断⇒集中⇒中断」が繰り返されるのはかなり疲れる。大した作業をしていなくても繰り返されることで夕方には頭がへとへとになる感覚がある。
職場環境がミスを誘発することもある
職場の環境自体が集中を妨げることもある。私のデスクの後ろでは、しばしば立ち話(業務の相談や雑談)が行われることがある。真後ろで会話が続いていると、どうしても気が散り、その結果、些細なミスが発生する。
不思議なことに、周囲の同僚たちはこうした環境でも平然と業務をこなしている。私からすれば、ミスもせず、よく疲れないで済むものだと感心してしまう。
周囲の音への過剰な反応、過集中と注意力散漫の繰り返しによるミスは、ASDやADHDの特性に起因するのかもしれない。
私なりの対策
対策①:電話を避ける
電話は突発的にかかってくるうえに、作業を完全に遮断される。さらに私の場合、吃音(難発性)の傾向があるため、急な電話対応は言葉に詰まることがある。
そのため、対策の一つとして作業中は業務用の携帯電話の音量をオフにしておく。電話がかかってきた場合は後から折り返す。こちらから電話を折り返すことで、あらかじめの準備もできるので、吃音のリスクも軽減できる。
しかし、厄介なのは内線電話である。
こちらは着信を避けようがなく、言葉が詰まる可能性もある。
さらに、他の人宛ての電話でその人が不在の場合、「誰かが出るべき」という暗黙のプレッシャーがある。しかも、作業中は頭がスムーズに切り替わらないため、電話が鳴ってもすぐに反応はできず、「電話が鳴ったらすぐ出ろ」と叱責されることもある。。
対策②:静かな場所に移動する
次の対策として、どうしても集中して作業したい場合、私は個室など静かな場所に移動するようにしている。上司に「集中して作業したいので個室にこもります」と伝えれば、多くの場合は理解してもらえる。
ただし、すべての上司が理解あるとは限らない。以前の部署では、「席を外すことが多すぎる」と怒られた経験がある。部下を細かくマネジメントしたいという上長の場合、この対策を取ることで、信頼を損なうおそれもある。
実際にあったエピソード
集計作業中の連続中断
細かい集計作業の取りまとめ中、次々と雑務が舞い込んできた。
- 「○○の雑誌が届きました、回覧をお願いします」
- 「○○の募金の件です」
- 「○○の備品が足りません、発注をお願いします」
こうした些細な用件で作業を中断させられるのは本当にストレスである。私としては「雑誌はそこに勝手に置いておいてくれ」「備品が足りないならメールでくれ」と思ってしまう。
これらが繰り返されることで集中が切れ、「今まさに修正しよう」と思ったことを忘れてしまったり、「後で確認すべき事項」を忘れるという失態も起こる。「やるべき事は都度、メモを取れば」という意見もあるかもしれないが、突然声をかけられることで、メモを取るという行動自体を失念してしまうこともある。
その結果、完成した集計にはミスが多く、上司からやり直しを命じられることは日常茶飯事である。
雑談による集中力の断絶
ある日、私は自席で社外業者と契約の電話調整をしていた。契約ということで、電話に集中する必要もあったし、メモを取る必要もあった。そのような中、背後で数名の社員が雑談を始め、突然大声で笑い出した。その結果、集中力が飛び、調整していた契約の内容が頭からすっぽ抜けてしまった。
私は思わず「うるさい!静かにしてくれ!」と強い口調で言ってしまった。電話口の相手にも聞こえるほどの声だったと思う。雑談をしていた社員も驚いたのか、その後は私に対して冷ややかな視線を向けるようになった。
一時の感情に任せた行動ではあったが、集中を妨げられることにストレスを感じてしまった。
以上、私のケアレスミスの傾向と、その対策、そして実際の体験をまとめてみた。
おそらく、ASDやADHDの傾向を持つ方々の中には、私と同じような経験をされた方も少なくないのではないだろうか。
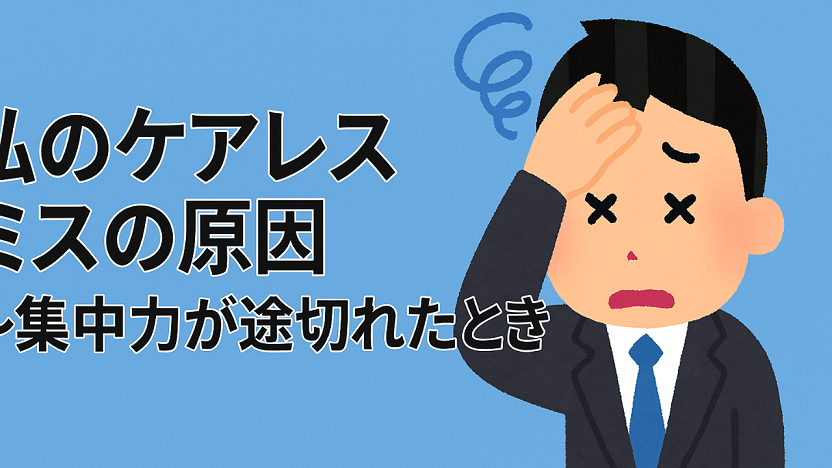
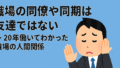

コメント