評価されなかった前任部署の私
先日投稿した「相性が最悪だった係長との仕事 ~万能型係長との決定的ミスマッチ」でも触れたが、私は前任の部署において、どれだけ努力しても評価されなかった。昇級もなく、成果として認められた実感は一切なかった。それどころか、ミスの多さや空気を読めない振る舞いばかりが目立ち、「使えない人間」「仕事のできない人」としてレッテルを貼られていたように思う。
そんな状況でも、自分を見失わないために「ダメ人間にも存在意義があるのではないか」と真剣に考えたことがある。以下は、私が導き出した考察である。
ダメな奴がいるから優秀な人が生まれる
会社組織においては、昇進や昇給といった人事評価が避けて通れない。社員全員に高評価をつけるわけにはいかず、必ず優劣をつけ、ランク分けしなければならない。いわゆる相対評価の世界である。
当然ながら、ランキングの上位者がいれば、必ず下位者も存在する。数値で明確に成果が出る業務であれば、比較的フェアに評価できるが、私が働いているような電力会社のように、業務成果を数値化しにくい場合は、評価が非常に難しい。
上司にとって、人事評価は重たい業務である。特に、部下全員が目立ったミスもなく、そつなく業務をこなしている場合、誰を高評価にし、誰を低評価にするか非常に悩ましい。全員に横並びで同じ評価をつけるわけにはいかない以上、何らかの差をつける必要があるからだ。
このような状況で、明確に「使えない」と認識されている社員が一人でもいれば、上司にとっては評価作業がぐっと楽になる。すでに職場内で「ダメな人」という共通認識がある人間ならば、最低評価を与えても納得を得やすい。他の部下に対しても「あの人よりはマシ」といった相対的評価で説明がつく。
さらに、上司自身もさらにその上司――部長や本部の人事担当者に対して、「この人物はこういう理由で最低評価です」と説明がしやすい。明確な欠点がいくつも挙げられ、低評価を付けるための根拠も作りやすいというものだ。
特にASDやADHD、吃音などの発達特性を持つ人間は、「低評価のつけやすい対象」として扱いやすいのだと思う。当時のグループ長にとって、私の存在は迷うことなく「最低評価」をつけられる便利な存在だったのではないかと考えている。
そういう意味では、私は前任の部署において、上司の人事評価業務の効率化に一役買っていたとも言える。自分の存在が「その他の社員を評価しやすくする」ための材料になっていたのだとすれば、皮肉ではあるが、一つの貢献だったのかもしれない。
ダメ人間がいることでチームはまとまる
学校生活を振り返ってみても、「一人の問題児」や「悪者」の存在がクラスの結束を高めるきっかけになった、という経験を持つ人は多いのではないだろうか。会社という組織においても、それに似た構造が存在しているように感じる。
職場でも「仕事ができない社員」「何かとミスが多い社員」といった「悪役」がいると、他の社員同士の一体感が生まれることがある。「○○さんのせいで…」「あの人がいなければうまく回るのに」といった共通認識が、ある種の連帯感を醸成するのだ。
さらに、「自分が叱られるのではなく、代わりに誰かがいつも叱られてくれる」という安心感から、他の社員が救われる場面もあるだろう。こうした「叱られ役の存在」が職場にいることで、結果として他の社員のストレスや不安が軽減されているとも言える。
この構図は、いじめのメカニズムや江戸時代の身分制度で「士農工商のさらに下に位置する存在」を作ることで農民の不満を抑えていた構造と、どこか似ているように感じる。
また、人は誰しも自分より劣っている存在を見ることで、相対的に安心感や優越感を得ようとする傾向がある。「あの人よりは自分の方がマシだ」と思える存在がいることで、自己肯定感を維持できることもある。これもまた、人間の本能的な側面なのかもしれない。
以上を踏まえると、組織における「ダメ人間」の存在は、チームの団結を促し、他の社員のメンタル維持やモチベーションの確保といった副次的な効果を生み出しているとも言える。私自身がその役割を担っていたのだとしたら、皮肉ではあるが、何らかの意味で前任部署のメンバーに貢献していたのかもしれない。
パレートの法則と「2割のダメ人間」
「パレートの法則」や「働きアリの法則」によれば、どんな組織にも2割の優秀な人、6割の普通の人、そして2割のダメな人が存在するとされる。たとえ優秀な人材だけを集めても、結局はその中から2割のダメ人間が生まれてしまうのだ。そういう意味では誰でも「ダメ社員」の烙印を押される可能性があると思う。
特に成果が数字で表れにくい職場では、上司の好き嫌いや相性によって評価が左右されることも少なくない。私自身、当時の上司と相性が悪く、その結果として「ダメ人間の枠」に押し込まれたと感じている。
組織において一度レッテルが貼られると、それをはがすのは容易ではない。たとえ異動があっても、前任部署の評価は引き継がれ、印象は残り続ける。転職でもしない限り、評価を覆すのは困難であるというのが、実感としてある。
私の考察 ダメ人間にも組織での役割がある
どれだけ努力しても評価されず、怒られ、無視されるような日々が続いたとき、自分を守るために考えざるを得なかった――「ダメ人間にも、存在意義があるのではないか」と。
今ではこう考えるようにしている。
- ダメ人間は上司の人事評価の負担軽減に貢献している
- チームの団結力や他の社員のモチベーション維持にも一役買っている
- 誰しも、職場環境と上司や同僚との相性次第で「ダメ人間」になりうる
以前の職場で明らかに「その役割」を担わされていただけかもしれない。そう思うことで自分の存在にも多少の意味を見出していた。
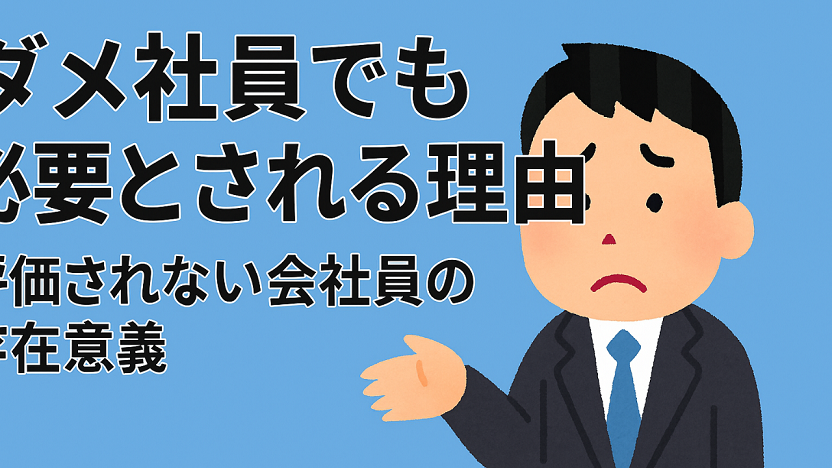
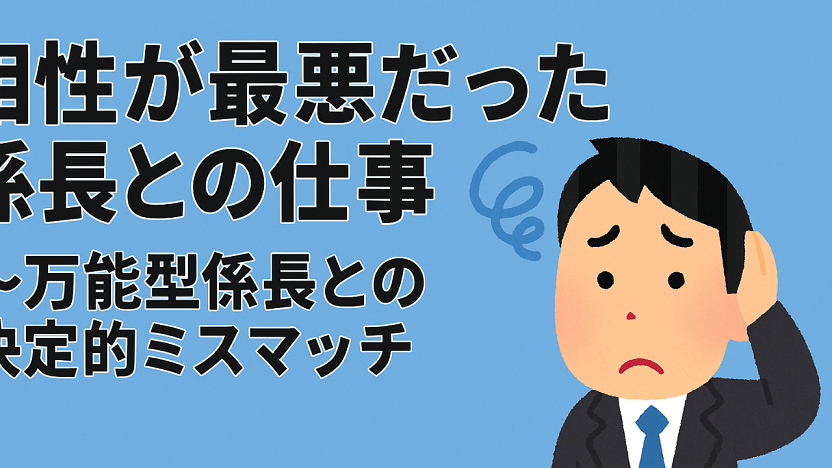
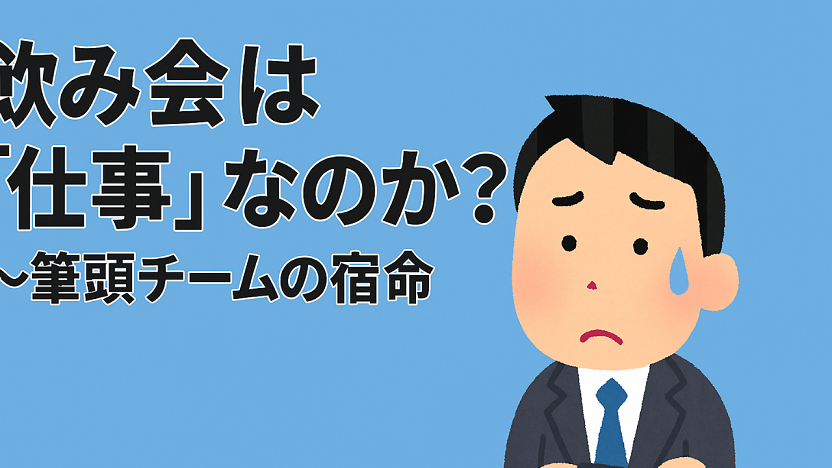
コメント