本記事は、私の電験三種勉強法シリーズの第3弾である。
第1弾では「前提条件と基礎知識」、第2弾では「理論科目の攻略法」について述べた。今回は、電験三種4科目のうち「機械科目」の勉強方法を紹介する。
理論科目の学習を終えた時点で、すでに学習習慣が確立し、数学と物理の基礎知識も身についているはずである。これらの下地があれば、機械科目の学習は比較的スムーズに進むと感じた。
私が感じた機械科目の特徴
●範囲がとにかく広い
機械科目は、「機械4機(直流機・誘導機・同期機・変圧器)」を中心に、パワーエレクトロニクス、制御、情報、照明、電熱、電動機応用、電気化学と、非常に多くの分野を学ばなければならない。
●計算問題は少なめ
私の感覚では、純粋な計算問題は全体の3~4割程度だった。理論科目のように高度な計算力や数学的センスを求められる問題は少なく、パターン化された問題も多い。
●思考型問題の存在
パワーエレクトロニクスの波形選択や制御・情報分野の問題は、順序立ててステップを踏み、論理的に解く形式が多かった。問題文が複雑そうに見えても、落ち着いて考えれば解ける場合もあった。
●論述問題が厄介
意外に厄介なのが論述問題である。特にマニアックなモーターの原理や制御方法など、文章量の多い問題が出題され、知識だけでなく読み解く力も問われる。失点しやすいのはこの論述問題だと思う。
●努力が報われやすい
範囲は広いものの、学習を続ければ確実に点数が伸び、安定しやすい科目だと思う。理論科目のように「ひらめき」や「直感的な発想力」を求められることは少なく、比較的素直な問題が多いと感じた。
学習前の準備、勉強ステップ
準備、ステップは理論科目の方法同様
準備と勉強ステップは基本的に理論科目で紹介した方法と同様である。詳細は「理論科目の攻略法」を参照してほしい。
● 準備したもの
- 参考書:『みんなが欲しかった! 電験三種 機械の教科書&問題集』
- 過去問集:『みんなが欲しかった! 電験三種の10年過去問題集』
- YouTube:特に「電験合格」チャンネルの解説が非常に分かりやすい。
- 計算用紙・ノート:計算や回路図の書き出しは必須。
- 電卓:平方根(ルート)機能付きの一般電卓(関数電卓は不可)。
● 第1弾 単元学習:参考書+YouTube+演習
① 参考書で単元学習
② YouTubeで視覚的に理解(電験合格、Aki学長)
③ 参考書の問題集で演習
● 第2弾:過去問演習
①年度ごとに過去問を解く
②1周目は1問ずつ解答と解説をじっくり読む。YouTubeも活用した。
③手を動かして解く。特に思考型問題は図示して解くと良い
それなりに時間は要するが、理論科目に比べ、2周目以降はテンポよく進められると思う。
全分野を学習する
機械科目は範囲が広いため、部分的に捨てる戦略を取る人もいる。だが私は次の理由から全分野を満遍なく勉強する方が良いと考える。
- 機械4機集中型のリスク
機械4機は確かに出題割合が高いが、難解な問題も混ざるため、すべてを得点することは困難である。特に論述問題はマニアックなものが出ることがあり分からなければ勘で選ぶしかない。 - パワエレ捨て戦略は危険
パワーエレクトロニクスはB問題で高確率で出題される。これを捨てると2問分の点数を落とすことになる。パワエレはむしろパターン化されている問題が多く、学習すれば得点源になる。 - その他分野にも易問がある
照明や電熱、電気化学などは、公式や基礎知識で解ける問題が多い。短期間の学習でも得点可能な場合がある。しかもB問題の選択として出題されることが多い。
学習期間と結果
私は機械科目を、毎日1〜2時間、約7か月間(9月開始、3月試験)勉強した。この間、電力科目の学習も並行して行っていたが、あくまで機械科目をメインとした。
理論科目のように苦戦することはなく、本番では85点を取ることができた。
また、機械4機やパワーエレクトロニクスの原理の勉強は意外に興味をひかれた。興味を持って学習できたことも、理論科目ほど苦戦しなかった理由の一つだと思う。
【参考記事】
電験三種の勉強法① ~前提条件と基礎知識の整理
電験三種の勉強法② ~理論科目の攻略法
電験三種の勉強法④ ~電力科目の攻略法
電験三種の勉強法⑤ ~法規科目の攻略法
電験三種の勉強法⑥ ~総括
【私が使用した参考書】
みんなが欲しかった! 電験三種 理論の教科書&問題集
みんなが欲しかった! 電験三種 電力の教科書&問題集
みんなが欲しかった! 電験三種 機械の教科書&問題集
みんなが欲しかった! 電験三種 法規の教科書&問題集
みんなが欲しかった! 電験三種の10年過去問題集

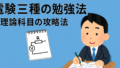

コメント