本記事は、私の電験三種勉強法シリーズの第4弾である。
第1弾では「前提条件と基礎知識」、第2弾では「理論科目の攻略法」、第3弾では「機械科目の攻略法」を紹介した。今回は、4科目の中でも比較的とっつきやすいと言われる「電力科目」の勉強方法について述べる。
電力科目は、発電・送電・配電の仕組みや設備の構造、運用方法を学ぶ分野である。
日常生活で目にする送電線や鉄塔、電柱といった設備も多く、イメージしやすい点が学習の取りかかりやすさにつながっていると思う。
私自身、幸いにも新入社員の頃に火力発電所の三交代勤務を経験していたため、火力発電に関する基礎知識はある程度あった。そのため火力発電の単元では学習の際に大きな助けとなった。
私が感じた電力科目の特徴
●論述問題が多い
電力科目は、発電方式や送配電システムの知識を問う論述問題が多く、知っていれば解ける問題も多い。しかし選択肢形式であっても、文章を正確に読み取る力は必要である。
●計算問題は3〜4割程度
純粋な計算問題は全体の3~4割程度で、機械科目と同程度の比率である。
ただし火力発電の効率計算など、一部の計算問題には独特のクセがある。特にkW・kWhといった単位がわかりにくく混同しやすい。
●勉強時間は比較的少なくて済む
4科目の中では勉強時間が最も少なくて済む科目だと感じた。
特に火力発電関連の論述問題は、私の場合は経験による知識があったため、参考書を一読する程度で済ませることができ、学習時間を削減できたと思う。
●短期間で仕上げたい科目
暗記要素が多い科目であるため、論述問題は試験直前の集中的な復習でも得点が伸びやすい。
私にとっては「時間をかけずに仕上げたい科目」だった。
私の勉強ステップ
電力科目の学習については、正直なところ、私の方法はあまり模範的ではないかもしれない。
機械科目の勉強をメインとし、その合間に気分転換として電力を学ぶ形だったからである。
●並行学習
機械科目を1〜2時間勉強した後、余裕があるときに気分転換で30分〜1時間程度を電力科目を学習していた。机に向かって勉強するときは計算問題を中心に取り組んだ。
●知識問題の学習方法
隙間時間に参考書を読んでいた。また移動中にはYouTubeの「電験合格」チャンネルを視聴し、視覚的に理解を深めるようにしていた。
動画で学ぶと、設備や機器のイメージがつかみやすく、文章だけよりも記憶に残りやすい。
●過去問演習
過去問は5年分のみ、しかも1回しか解かなかった。
重点的に取り組んだのは計算問題で、知識問題は一読して正解率を確認する程度にとどめた。
●試験直前の総復習
試験直前には『みんなが欲しかった! 電験三種 電力の教科書&問題集』の問題集を一読し、暗記系の知識を短期間で詰め込んだ。
最近の試験では過去問からの出題も多いため、本番では同じ問題や類似問題に助けられた。
学習の優先度と戦略
私にとって「2回目の受験は機械科目がメインで、電力科目は合格できればラッキー」という位置付けだった。
本来は3回目の受験で電力と法規を合格させるつもりでいたため、学習は機械科目の合間に行う方針とした。そのため、特に時間がかかりそうな計算問題を重点的に取り組むことにした。
学習期間と結果
私が電力科目に費やした期間は約7か月(9月開始、翌年3月試験)。
しかし実際の勉強時間は100時間にも満たないと思う。
メインは機械科目であり、あくまで「ついで」に学習していた。
それでも本番では70点を獲得できた。
運が良かった面もあるが、暗記系の出題に助けられたこと、火力発電の経験があったことが科目合格につながったと思う。
【参考】
電験三種の勉強法① ~前提条件と基礎知識の整理
電験三種の勉強法② ~理論科目の攻略法
電験三種の勉強法③ ~機械科目の攻略法
電験三種の勉強法⑤ ~法規科目の攻略法
電験三種の勉強法⑥ ~総括
【私が使用した参考書】
みんなが欲しかった! 電験三種 理論の教科書&問題集
みんなが欲しかった! 電験三種 電力の教科書&問題集
みんなが欲しかった! 電験三種 機械の教科書&問題集
みんなが欲しかった! 電験三種 法規の教科書&問題集
みんなが欲しかった! 電験三種の10年過去問題集

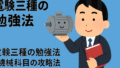
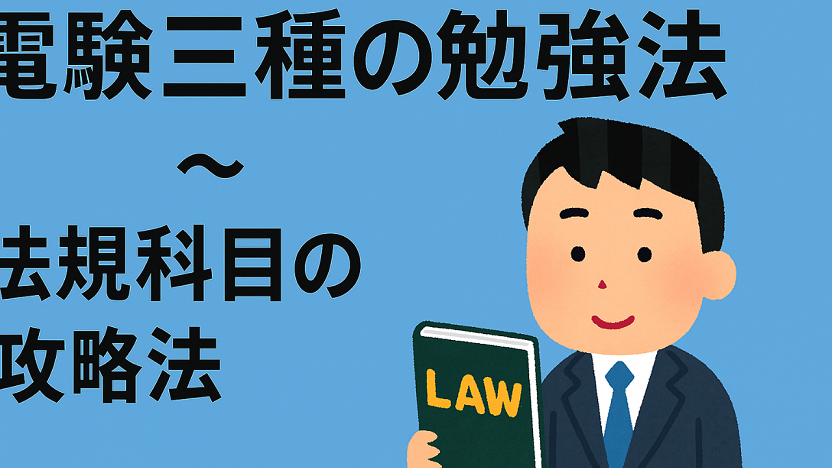
コメント