貯金から始まる資産運用
私は20年以上にわたり資産運用を続けている。しかし、投資や運用を始めるには「元手」が必要である。そもそも投資にはある程度の種銭が必要である。今振り返っても、若い時に「貯金習慣」を身につけられたことが、その後の人生を大きく左右したと感じている。今回は、新入社員の頃に得た貯金の大切さについて記録しておきたい。
新入社員の給料と財形貯蓄
社会人になりたての頃、私は毎月17万円ほどの給料を受け取っていた。当時の私にとって、毎月10万円以上が安定して振り込まれることは未知の感覚であり、給料の使い道を考えるだけでワクワクした。
新入社員研修の前半では、会社から給料や財形貯蓄の説明があった。おそらく新入社員が給料を散財せず、最低限の貯金習慣を持つよう注意喚起する狙いがあったのだろう。実際、同期の多くは「1〜2万円程度を財形で貯金すればよい」と考えていた。私も同じで、年間数十万円も貯まれば十分だと安易に考えていた。
部署配属研修での出会い
ところが、研修終盤の「職場体験研修」で配属された部署の、ある係長からのアドバイスが私の考え方を大きく変えた。私は研修の一環として、配電関係の部署に2週間ほど配属された。その係長からのアドバイスは次のようなものであった。
- 新入社員の給料などどうせ散財して消える。飲み代や遊びで無駄になるのが関の山だ。
- だからこそ、毎月5万円を財形で天引き貯金しろ。学生時代の生活レベルを維持すれば、それでも十分暮らせるはずだ。
- ボーナスも同様に、最低20万円は天引きで貯金しろ。ボーナスは特に気を抜けば散財するからだ。
- そうすれば年間100万円が貯まる。数年で数百万円になり、結婚や住宅購入、急な出費のときに必ず自分を助ける。
当時の私は「学生時代と同じ生活を続けるのは嫌だ」と感じた。しかし「年間100万円の貯金」という響きに大きな魅力を覚えた。新入社員にとって100万円は超大金であり、それが1年で貯まるという感覚は衝撃的だった。結果として、私はすぐに財形貯蓄の積立額を大幅に引き上げた。
3年間で300万円
このアドバイスを実践した結果、私は毎年100万円を貯めることに成功し、3年間で合計300万円の貯金を築いた。
「毎月5万円を天引きして本当に生活できるのか」と不安もあったが、実際には学生時代よりは少し余裕のある生活ができた。遊びにも出かけられたし、飲み会にもある程度参加できた。それ以上に、毎月残高が増えていく感覚が楽しく、特に100万円を突破したときの達成感は忘れられない。
新入社員研修自体はあまり良い思い出がなかったが、この係長のアドバイスは私の人生において大きな財産となったと思う。
300万円がもたらしたもの
一人暮らしをしていた当時の私にとって、300万円という額は大きな安心感をもたらした。車を購入することもできるし、住宅購入を考える際の頭金にもなる。さらに、株式や投資信託、不動産など、さまざまな投資にも挑戦できる。
仮に会社を辞めることになっても、300万円あれば数年は生活できるだろうという心理的な支えも大きかった。そして何より重要なのは、貯金習慣が生活の一部として定着したことである。
今でも私は財形で毎月4万5千円、ボーナス時に20万円を貯金している。さらに積み立て投資として、全世界株式インデックス(オルカン)に年間5万円を追加している。新入社員の頃に培った習慣は、今でも資産形成の基盤として生き続けている。
若手社員へのアドバイス
ここまでの経験から、若手社員が私にアドバイスを求めたら貯金習慣の大切さを伝えると思う。
「貯金習慣は早ければ早いほど、将来の自分を助ける強力な武器になる」ということだ。
最初は数万円で構わない。重要なのは「自動的に貯金される仕組み」を作ることだ。給料から天引きされてしまえば、残りのお金でやりくりするしかなくなる。人間は意志の力で節約を続けるのは難しいが、仕組みさえ作れば自然に貯まっていく。
投資や資産運用は華やかに語られるが、種銭がなければ始められない。まずは貯金という基盤を築くことが最優先である。貯金があることで精神的な余裕が生まれ、「最悪辞めても数年は生活できる」という自信につながる。
もしあの時、係長のアドバイスを素直に聞かなければ、私は給料を無駄に散財していたと思う。しかしそのアドバイスを聞くことで、資産形成の第一歩を踏み出すことができた。まずは「貯金の仕組み」を早くつくることを勧めたい。その習慣が、数年後には大きな安心感と可能性となって自分を助けると思う。
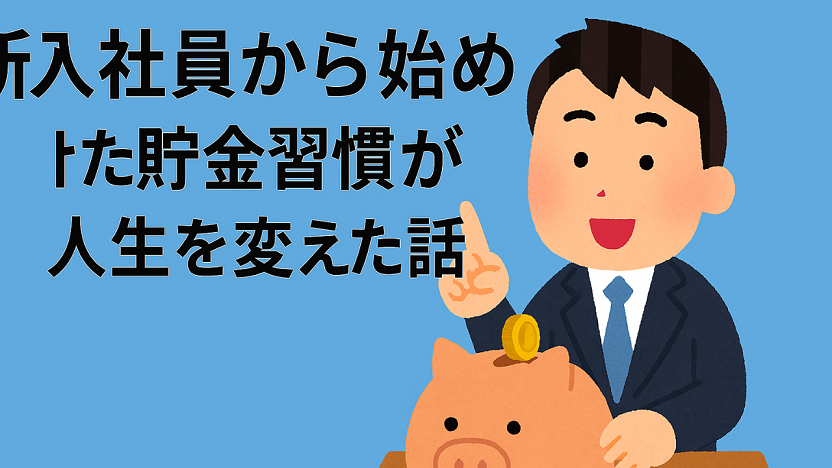
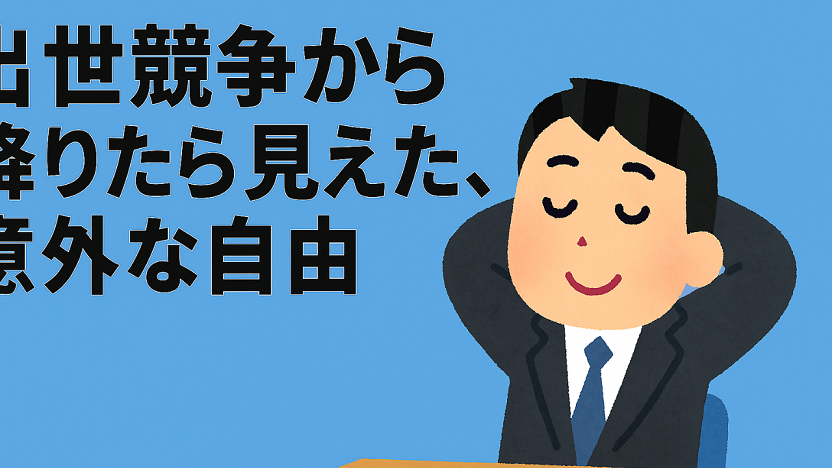
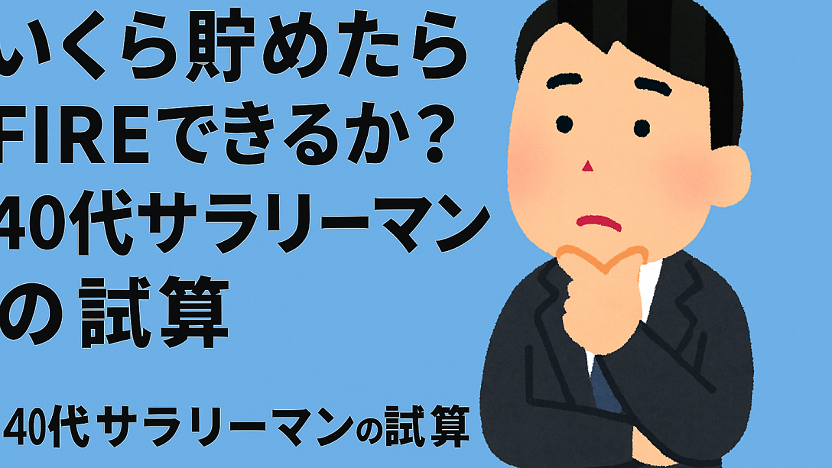
コメント