会社を辞めたらどうなるのか?社会保険制度や税金の観点から考えてみた。
このテーマは早期退職やFIREを考える人にとって注意しなくてはならないことも多いと思う。資産があれば生活費をまかなえるかもしれないが、一方で社会保障や税金の制度は必ず関わってくる。
制度を理解しておかないと、思わぬ出費で資金計画が崩れたり、もらえるはずのお金がもらえなかったなんてことにもなり得る。
今回は、私自身の備忘録も兼ねて、退職後に関わる社会保障や制度について整理してみたい。
健康保険 ― 継続か切り替えか
まず考えなければならないのが健康保険である。この健康保険料が意外にばかにならない額である。会社を辞めると自動的に資格を失うため、自分で加入先を選ぶ必要がある。
選択肢は大きく2つ。
- 任意継続:これまでの会社の健康保険を最長2年間だけ継続できる制度。ただし保険料は全額自己負担になるため、現役時代より高くなる。
- 国民健康保険:市区町村が運営している保険で、世帯の所得に応じて保険料が決まる。扶養という概念がなくなるので、家族全員分の保険料が必要になる。
どちらが得かは人それぞれである。医療費が多いなら任意継続、所得が下がるなら国民健康保険の方が安い場合もある。いずれにせよ、辞める前に試算しておく必要があると考える。
年金 ― 厚生年金から国民年金へ
現役の会社員は厚生年金に加入しているが、退職すると自動的に国民年金に切り替わる。
国民年金の保険料は月額約17,000円程度(令和7年度時点)。妻の分を含めると家計にはそれなりの負担になる。もし支払いが難しい場合は、免除や猶予の制度もある。収入が減り困ったときは市区町村に相談するのも一案だと考える。
また、将来の年金額を増やしたい人は「付加年金」や「国民年金基金」を活用する方法もある。退職後の生活資金と老後資金は直結しているため、ここも事前に情報収集が必要と考える。もしかしたら、年金額の増額に期待するより、全世界株式インデックス(いわゆるオルカン)などを活用した資産運用などを活用した資産運用の方が良いかもしれない。
雇用保険(失業保険) ― 自己都合か会社都合か
退職後の収入源として大きな意味を持つのが雇用保険である。いわゆる「失業手当」だ。
注意すべきは、退職理由によって給付条件が大きく変わることだ。
- 自己都合退職:3か月の待機期間の後、給付が始まる。給付日数は90日〜150日程度が一般的。
- 会社都合退職:待機期間なしですぐに給付が始まる。さらに給付日数が長く、勤続年数や年齢によっては最大330日も受給できる。
つまり、リストラで辞めるのと早期退職で辞めるのとでは大きな差が出る。制度上は「会社都合」の方が圧倒的に有利だ。そのように考えると、早期退職希望者にとっては会社都合になるリストラも悪い話ではないのかもしれない。
職業訓練 ― スキルアップしながら給付延長
あまり知られていないが、ハローワークが実施する「職業訓練(ハロートレーニング)」を受けると、失業給付を受けながらスキルを身につけることができる。訓練期間中は給付期間が延長されるため、実質的に失業手当を長く受け取れる仕組みになっている。
パソコンスキル、簿記、プログラミングなど多様なコースがあり、受講料は無料のものも多い。再就職や副業、リスキリングの準備にもつながるので、早期退職後の選択肢としても良いと思う。
税金関係 ― 思わぬ出費に注意
退職後に意外と負担感があるのが税金である。
まず住民税。前年の所得に基づいて翌年に請求されるため、退職後もしばらくは高額な請求が来る。場合によっては退職後すぐに一括払いの通知が届き、資金計画を狂わす原因になる。そのため、退職前には住民税のための生活防衛資金を準備しておきたい。
また、退職金については「退職所得控除」という優遇制度がある。勤続年数に応じて大きな控除が受けられるため、通常の給与所得より税金はかなり軽くなる。これは退職者にとってありがたい制度である。ただし、近年、退職金にかかる税制の改悪が検討されていたり、iDeCo(個人型確定拠出年金)受け取りのルールが変更されるので注意したい。
まとめ ― 制度を知れば安心につながる
退職後に直面する制度を整理してみたが、こうして並べてみると結構複雑で「知らないと損をするもの」が多いと感じる。
- 健康保険は任意継続か国保かを選ぶ必要がある
- 年金は国民年金に切り替わり、免除や付加制度も活用できる
- 雇用保険は退職理由で条件が大きく変わる
- 職業訓練は給付延長+スキル獲得のチャンス
- 税金は住民税や退職金の扱いに注意
結局のところ、退職には『資産』だけでなく『制度の理解』も欠かせないと感じる。知らなかったために余計な税金や社会保険料を取られるのは避けたいものである。
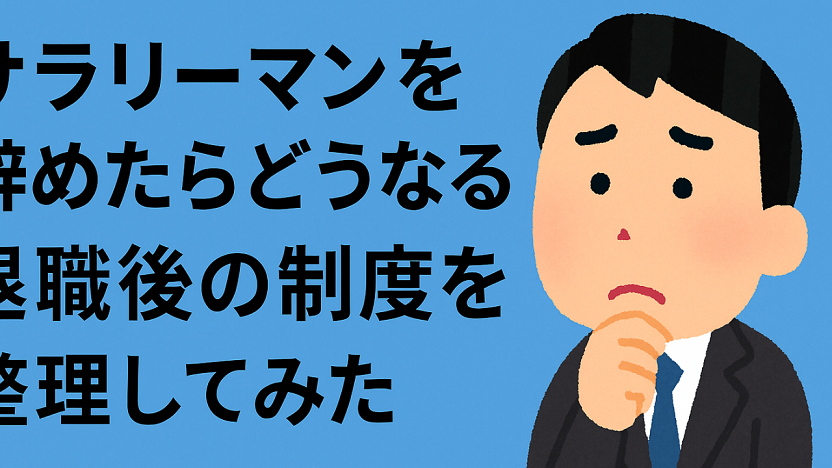
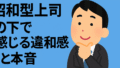
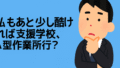
コメント