電験三種とは
電験三種(第三種電気主任技術者)は、電気設備の保安監督を行うために必要な国家資格である。試験は「理論」「電力」「機械」「法規」の4科目から構成され、3年以内に全科目を合格しなければ資格が取得できない。
この資格は一定の難易度がある資格として知られ、電力会社では保有者が一定数いるものの、合格率は決して高くない。私の勤務先でも、電験二種・一種を含めれば、5人に1人程度が保有している感覚である。
電力会社では、三種は電気技術者の登竜門とされており、保有していれば「一人前の電力社員」として扱われる風潮がある。
ちなみに、電験二種は三種以上の難関であり、取得すれば社内でも一目置かれる存在となる。さらに電験一種に至っては「神のような存在」であり、社内報で大々的に紹介され、社長からの表彰もあるほどである。
電験に興味を持ったきっかけ
私が電験三種に興味を持ったのは、前任の部署の再エネ設備管理業務がきっかけであった。当時、若い社員と現場へ同行することが多く、車中でよく電気の話をしていた。その若手社員は国立大の大学院卒で電磁気学を専攻し、高身長でイケメン、まさに非の打ち所のない人物であった。
一方、私は理系大学は卒業しているものの、これまで物理を選択してこなかったため、電気や電磁気に関しては素人であった。しかし、彼は素人にもわかるように電気の理論を教えてくれた。「なぜこの装置があるのか」といった現場での疑問にも的確に答えてくれ、私の電気への興味が少しずつ芽生えてきた。
その頃、職場には電験三種の勉強をしている別の若手社員もおり、彼の姿を見て「私も受けてみようか」と思うようになった。しかし、参考書を開いてみると難解な数式や専門用語が並び、「これは無理だ」と感じたのも事実である。
受験を決意するまでの経緯
私にとって電験三種の合格は、3年以上の継続的な勉強が必要と感じられるほどの難易度に見えた。
だが、ちょうどその頃、試験制度の見直しがあり、従来は年1回の試験で3年以内に4科目合格という条件だったが、年2回実施に変更されたのである。合格条件こそ変わらないが、受験機会が倍増したことは、受験者にとって有利な条件となった
変更の背景には、将来的な電気主任技術者の不足があるという。いわゆる人手不足である。この制度変更により、「今がチャンスではないか」と思った。また、資格があれば、将来リストラされても最低限の仕事には困らないかもしれない。転職エージェントに相談した際にも、電力会社勤務の経験者は「電気がわかる人」として評価されるらしく、電験三種は最低限必要との助言を受けたことも後押しとなった。
そうして私は、45歳の冬、電験三種への挑戦を決意したのである。
合格までの道のり
約1年半にわたる挑戦の結果、私は3回の受験で4科目すべてに合格することができた。
- 1回目:理論
- 2回目:電力・機械
- 3回目:法規
この順序は、書籍やブログなどでも「王道」とされている。特に理論は一番最初に勉強した方が良いととのことであった。
最後の「法規」の合格が分かった瞬間は本当に嬉しかった。制度の緩和に助けられた面もあるが、「こんな私でも取れた」という達成感があった。40代半ばからでも挑戦できたのは、年齢よりも「興味」と「継続」の力が大きいのだと実感した。もしかすると、私のASD傾向が「集中力の継続」という形で良い方向に働いたのかもしれない。
かつて現場で電気を教えてくれた若い社員、電験三種を勉強していた別の社員も、私の合格を心から祝ってくれた。中年の「ダメ社員」と思っていた自分に、刺激ときっかけを与えてくれた彼らには深く感謝している。
電験3種を取得して
決して簡単な試験ではないが、着実に努力を積み重ねれば到達可能な資格であると実感した。特に、制度が緩和された今こそ、この資格を取得するチャンスであると思う。
今回の合格に当たり、私の具体的な勉強法や使用した教材については、別の記事で紹介していきたいと思う。これから受験を考えている方の参考になれば幸いである。
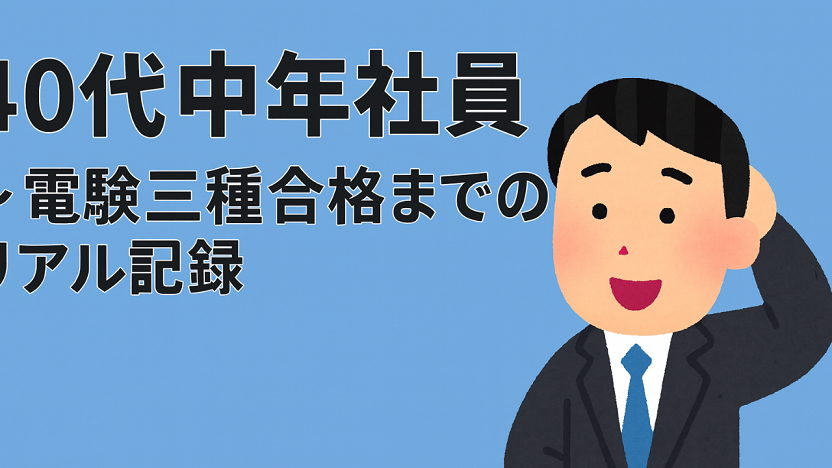

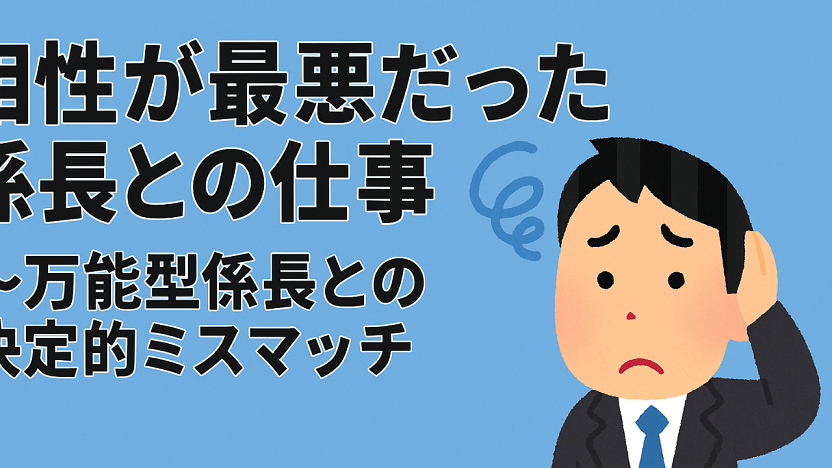
コメント