本記事では、私の電験三種の勉強方法について紹介する。
電験三種は「理論」「電力」「機械」「法規」の4科目で構成されており、各科目対策方法が異なるため、私の備忘録も兼ね、複数回に分けて記事にまとめる予定である。
まず今回は、勉強に入る前の「私の受験時の前提条件」や「必要な基礎知識」について述べたい。
私の受験時の前提条件
学習法や合格までに必要な勉強時間は、受験者自身の「基礎知識」や「学歴・専攻」よって大きく左右されると思う。以下に、受験前の私の状況を記しておく。
- 理系の大学院(専攻は化学)を卒業しているが、電磁気関係の科目は一切履修していない
- 高校では化学と生物を選択し、物理は未履修
- 大学入試も理科は化学で受験している
- 数学については、高校で数学Ⅲ(極限・微積分)、数学C(曲線・行列)まで履修したが、大学入学以降はほとんど触れておらず、微積分の内容は完全に忘れていた
このような状態から勉強を開始し、結果として1年半の勉強期間で全4科目を合格することができた。
電験受験に必須な基礎知識とは?
数学、物理の基礎が必須
電験三種の勉強を始めるにあたり、数学と物理の基礎知識が必要である。特に一番最初に学習した「理論科目」は、数学、物理の基礎がないと解説すら理解できず、正直キツイ。
もしこれらの基礎知識が欠けていると、参考書や問題集に取り組んでも内容が理解できず、躓くたびに数学物理の基礎を確認しなくてはならないため、学習が思うように進まなないと思う。
私自身も理論科目では理解が進まず苦労し、数学の忘れていた部分や物理の未習部分を、都度ネットで調べながら学習するという非効率な方法で進めていた。今振り返れば、事前に基礎を勉強してから理論に取り組めば、もっと効率的に学習できたのではと思っている。
必要な数学の範囲
電験三種に必要な数学の知識は、高校2年程度までの範囲で足りる。しかし、すべての高校2年までの分野を学ぶ必要はない。主に以下のテーマを押さえておけば、電験三種は乗り越えられると思う。
- 平方根の計算
- 指数法則、指数の計算ルール(10のn乗など)
- 三角比・三角関数(sin、cos、tan)
- ベクトル
- 複素数(a + jb 形式)
微分積分も必要だと言われることがあるが電験三種では不要だと思う。だが概念だけでも知っておくと理解に役立つと思う。特に実効値や過渡現象を学ぶ際に、微分積分の概念が役に立ったと思う。
また、「対数」はあまり使わないが、理論科目や機械科目で「利得(dB)」を計算する問題が出ることがある。出題頻度は高くないが公式さえ覚えていれば解ける問題も多いので、余裕があれば覚えていて損は無いと思う。
一方で、以下の分野は基本的に不要である。
- 数列、漸化式
- 確率・統計
- 証明
必要な物理の範囲
物理については、特に電磁気学の知識があると非常に有利である。というのも、電験三種という試験自体が電磁気を中心に構成されているからである。
加えて、以下のような力学の基礎知識も必要となる場面がある(特に理論科目で必要な知識である)。
- 速度と加速度
- 運動エネルギーと力学的エネルギー
- モーメント(力のモーメント、回転運動)
- 力と仕事
私の場合、物理の履修歴がまったくなかったため、力学の知識もなく、参考書や過去問に出てくる言葉、公式ひとつひとつを調べながらの勉強であった。結果として、物理の基礎が分からないため、かなりの時間と労力を要した。
おすすめの教材と活用方法
基礎が不安な場合 『みんなが欲しかった! 電験三種 合格へのはじめの一歩』
もし自分の数学、物理の基礎に不安がある場合は、電験の本格的な参考書に入る前に、基礎専用の教材を1冊購入し学習すると良いかもしれない。電験用の基礎教材は必要な数学、物理の範囲を絞った内容なので効率的に基礎が学べると思う。
- 例:『みんなが欲しかった! 電験三種 合格へのはじめの一歩』(TAC出版)
私自身、数学の記憶は比較的すぐに取り戻せたが、物理の知識についてはホームページやYouTubeでその都度調べながら進めていたため、非常に非効率だった。
基礎教材を購入しなかったが、今思えば、数千円の出費を惜しまずに体系的に基礎が学べる1冊を持っていた方が、結果的に早道だったと感じている。
私が使用した参考書『みんなが欲しかった!電験三種』シリーズ
私が使用した主な参考書は、TAC出版の人気シリーズ『みんなが欲しかった!電験三種』である。各科目・問題集ともに以下の通り活用した。
- 『みんなが欲しかった!電験三種 理論』
- 『みんなが欲しかった!電験三種 電力』
- 『みんなが欲しかった!電験三種 機械』
- 『みんなが欲しかった!電験三種 法規』
- 『みんなが欲しかった!電験三種 過去問題集(10年分)』
このシリーズは、イラストや図解が豊富でとっつきやすく、他の参考書に比べ初心者でも手に取りやすいと思う。ただし、内容自体は決して簡単ではなく、しっかり読み込む必要がある。参考書と問題集は分冊されており、問題集は分野ごとに整理されているため、復習しやすい構成となっている。
すべて揃えるとなると費用がかかる点は難点であるが、合格後に書き込みや汚れが少なければばメルカリなどで売却も可能である。
人気シリーズなので需要もあるのでそれなりの価格で売れると思う。
参考までに私の場合、4科目まとめてメルカリで出品したところ6500円で売れた。過去問題集(10年分)は1500円で売れた。
なお過去問は、電気技術者試験センターのホームページから無料でダウンロードすることもできる。
自宅にプリンターがあれば、無理に市販本を買わなくても問題はないかもしれない。ただし、10年分の過去問がまとめられた市販本を購入すれば、書き込みや繰り返し学習がしやすいというメリットもある。
YouTubeの活用も効果的
参考書だけでは理解できない部分も多いため、その際はYouTube動画を積極的にに活用した。動画は理論や仕組みを視覚的に説明してくれるので結果、非常に有用であったと感じている。
特に私は以下のチャンネルに非常にお世話になった。
- 電験合格(チャンネル)
→ テキストPDF付き。講義を受けている感覚で学べる。
- Aki塾長(チャンネル)
→ 図解と丁寧な解説で、特に物理が苦手な人にも分かりやすい。
動画はスキマ時間にも視聴できるため、通勤・昼休みなどの時間を活用したインプットにも最適であると思う。
具体的な勉強方法について
この記事は、物理未履修の私が、ゼロから電験三種合格を目指した記録である。基礎力に不安がある方の参考になれば幸いである。
次回以降は、各科目ごとの具体的な勉強方法や教材活用法について、さらに詳しく記載したいと思う。
【参考記事】
電験三種の勉強法② ~理論科目の攻略法
電験三種の勉強法③ ~機械科目の攻略法
電験三種の勉強法④ ~電力科目の攻略法
電験三種の勉強法⑤ ~法規科目の攻略法
電験三種の勉強法⑥ ~総括
【私が使用した参考書】
みんなが欲しかった! 電験三種 理論の教科書&問題集
みんなが欲しかった! 電験三種 電力の教科書&問題集
みんなが欲しかった! 電験三種 機械の教科書&問題集
みんなが欲しかった! 電験三種 法規の教科書&問題集
みんなが欲しかった! 電験三種の10年過去問題集

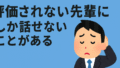
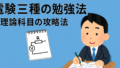
コメント