本記事は、前回の「電験三種の勉強法① ~前提条件と基礎知識の整理」に続く第2弾である。
今回は、電験三種の4科目のうち、理論科目の勉強方法について紹介する。
理論は「最初に勉強すべき科目」とされているが、初学者にとっては出鼻をくじく難関科目である。
そして、理解が進まず挫折してしまう恐れがある科目でもある。
私自身も理論科目に最初に取り組み、数多くの壁にぶつかりながらも、なんとか学習を習慣づけることができた。その結果、約8か月間の学習でギリギリながら合格点(60点)を取ることができた。
私が感じた理論科目の特徴
●最初に立ちはだかる難関
理論は勉強の入口であると同時に、最初の大きな壁でもある。序盤で行き詰まり、勉強が嫌になり挫折する人も多いと思う。
●計算問題が大半
出題の8割以上は計算問題。分数や文字式を含む複雑な計算式など計算力を求められる問題も出題される。さらに電気というより数学的なセンスや柔軟な発想力が問われる問題があるのも厄介である。
●機械科目よりも難しいと感じた
機械と理論は難科目と言われるが、私にとっては理論の方がはるかに高難易度だった。機械は理論のように数学的センスが求められる問題やひねった問題は少ないと思う。
学習前の準備
理論を学習するうえで、数学の基礎知識は必須である。もし参考書や問題集を読んで指数のルール等数学面で分からない箇所があれば、適宜ネットで調べるか、高校時代の数学教科書を活用すると良いと思うと思う。理論科目では数学の基礎が常に求められる。
準備したもの
●参考書
『みんなが欲しかった! 電験三種 理論の教科書&問題集』
教科書と分野別問題集がセットになっており、初学者に適している。
●過去問集
『みんなが欲しかった! 電験三種の10年過去問題集』
第2弾(過去問演習)から使用。
●電卓
平方根(ルート)機能付きで、試験で使用可能な一般電卓。関数電卓は使用不可。
●計算用紙・ノート
計算問題は必ず紙に書いて解く。暗算や頭の中だけで解くのは非効率で、ミスのもとになる。
勉強ステップ 第1弾:参考書+YouTube+演習
① 参考書で単元学習
- 「静電気」「電磁気」「直流回路」「交流回路」など単元ごとに進める。
- 最初から完璧を目指さず、参考書は一読して概要をつかむ。
- どうしても理解できない部分は飛ばして先に進んでもよい。
② YouTubeで視覚的に理解
読んだ単元を動画で学び直す。
私は当初Aki塾長の動画を見ていたが、後に「電験合格」チャンネルの方が分かりやすいと感じた。
再生速度は1.25〜1.5倍で効率化しても良いと思う。聞き逃した部分は巻き戻す。
③ 参考書の問題集で演習
- 該当単元の問題を解く。5分考えて解けなければ解説を読む。
- 解説を読んでも理解できなければ動画検索。
「電験 理論 平成●年 第〇問」で検索すると、解説動画が複数見つかる。
●勉強ステップ 第1弾の期間目安
私の場合、最後の単元(電気・電子計測)まで進めるのにかかったと思う。
疲れた日は参考書だけ読む、動画だけ視聴する日もあった。
勉強ステップ 第2弾:過去問演習
①過去問の使い方
●年度ごとに解く
第1弾では参考書にて分野別に勉強していたが、過去問では実際の試験と同じ形式で、年度ごとの問題を通して解く。これにより、分野の混ざった出題への対応力が養われる。
●最初は時間を測らない
初めから本試験時間を意識すると、焦って解説を飛ばしがちになる。最初の1〜2周は時間無制限で、一問ずつ丁寧に取り組む。
②解答と解説の見方
●1問ずつ区切る
まず1問ずつ自力で解き、答え合わせをしてから解説を読む。間違えたら、その場で理解できるまで深掘りする。そして次の問題を解く。
●理解できなければ動画で補強
特に計算過程や式変形が難しい問題は、YouTubeの解説動画が役立つ。「電験 理論 平成●年 第〇問」で検索すると複数ヒットするので、自分に合う説明を探す。
●手を動かすことを徹底
解説を読むだけでは理解が浅くなる。必ず紙に計算過程を書き、式を自分の手で再現する。
③得点推移の目安(私の場合)
●1周目:
年度ごとに通して解くと、正答率は2割以下(20点未満)
序盤に学習した分野を忘れているため、解けない問題が続く。
●2周目:
正答率が3〜4割程度に上昇
1周目で繰り返し見た公式やパターンが身につき、スピードも少し向上。
●3周目:
安定して合格ライン近く(5〜6割)
間違いが減り、計算にも慣れてくる。ここまで来れば本試験でも戦える。
④周回方法と期間目安
●1周目:
丁寧に理解重視。10年分を解くのに3か月以上かかった。1問の問題を解く、理解するのに1時間かかることもあった。
●2周目:
理解済みの問題はテンポよく進めることができると思う。解き方を忘れていた問題は再度復習する。おそらく2週目は、10年分を1か月~2か月程度で完了すると思う。
●3周目:
理解が定着していない問題の補強とスピード重視。試験形式を意識しながら通し演習を行う。3周目になると、1か月以内に終えることができると思う。
④繰り返しの重要性
過去問を繰り返す最大の効果は知識の定着にある
分野別学習だと、以前やった範囲を忘れることが多いが、年度ごとに解くことで毎回全分野に触れることになる。
また、出題形式や設問パターンに慣れることで、本試験の問題文を見た瞬間に解法の方向性が浮かぶようになる。
学習期間と結果
私は理論科目に絞り、毎日1〜2時間、8か月間(1月開始、8月試験)勉強した。
「これで取れなければ電験三種の取得を諦める」という覚悟で臨み、結果はギリギリ60点で合格。
初回試験で理論だけをクリアできた。
まとめ
- 理論は最初に学ぶべきだが、最難関科目でもある
- 計算問題が多く、数学的発想力が求められる
- 参考書→YouTube→問題集のサイクルが効果的
- 過去問は最低10年分×3周が目安
- 毎日コツコツ続けることで合格点は見えてくる
【参考記事】
電験三種の勉強法① ~前提条件と基礎知識の整理
電験三種の勉強法③ ~機械科目の攻略法
電験三種の勉強法④ ~電力科目の攻略法
電験三種の勉強法⑤ ~法規科目の攻略法
電験三種の勉強法⑥ ~総括
【私が使用した参考書】
みんなが欲しかった! 電験三種 理論の教科書&問題集
みんなが欲しかった! 電験三種 電力の教科書&問題集
みんなが欲しかった! 電験三種 機械の教科書&問題集
みんなが欲しかった! 電験三種 法規の教科書&問題集
みんなが欲しかった! 電験三種の10年過去問題集

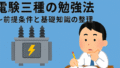
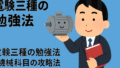
コメント