同僚や同期は「友達」なのか?
会社員生活を20年以上続けてきて、私が実感したことがある。それは「職場の同僚や同期は、基本的に友達ではない」ということである。もっと言えば、友達にはなり得ない関係なのだと思う。
職場では、確かに気の合う人や、親しくなる人に出会うことはある。しかしそれは、会社の業務という共通項があってこそ成立する一時的な関係であり、根本的には友情とは異なる。これはあくまで私の経験則だが、今までの実例をもとに、その理由を整理してみたい。
新入社員研修の「団結」は一時のもの
新入社員研修のときは、人事の意図もあったのか、同期同士で団結して盛り上がる空気が作られていた。そして、多くの同期は、研修後もしばらくは仲の良い関係を続け、一緒に遊んだり、飲みに行ったりするようである。
しかし、私の場合は事情が違った。研修後すぐに三交代勤務に配属されたことで、同期との接点がほとんどなくなった。その結果、同期の中では影の薄い存在となり、関係は自然と疎遠になった。
異動とともに薄れる関係
職場で親しくなった同僚も、どちらかが異動すれば関係は急速に薄れていく。とくに勤務地が異なる部署に異動すれば、物理的に顔を合わすこともなくなり、連絡も自然と減っていく。
相手も新しい環境に適応するのに精一杯であり、私自身も同様である。会社の業務が関係性の土台である以上、その接点が途絶えれば関係も消えていくのは仕方のないことだと思った。
対立部署への異動で生まれる距離感
たとえ親しい同僚であっても、異動によって利害が対立する部署に配置されることもある。部署が違えば立場も違い、業務上で対立する場面も出てくる。
もちろん、仕事とプライベートを切り分けるべきだという意見もある。しかし人間の感情はそう単純なものではない。現実には対立が続けば感情面に影響を与え、個人的な関係もギクシャクしていく。関係がギクシャクすれば、自然と距離を置くようになるものである。
出世競争がもたらす“無意識の距離”
職場は競争の場でもある。仲が良かった同期も、視点を変えれば昇進を争うライバルだ。
特に出世欲の強い人は、周囲を蹴落としてでも上を目指す傾向がある。そのような人との関係は、どこかでひずみが生まれる。
また、今の同僚であっても、数年後には上司と部下の関係になる可能性がある。
実際、私が親しくしていた同期も、今では係長や課長となっている。そのため、職場では「役職者」「目上の人」として接することになる。そして職場外の場でも無意識にそのように接してしまう。そうなると以前のような関係性にはもう戻れない。
退職すればすべては「過去の関係」
どれだけ仲が良くても、相手が退職すれば関係は終わる。退職の際に「これからも一緒に遊びに行きましょう」と言っていた人も、実際には遊びに行くことはなかった。
退職した相手も、次のステージで新たな生活を始め、前職の人間関係にまで気を回す余裕はないのだと思う。やはり、会社の関係性とは業務上のつながりであり、それが切れれば関係性も終わるのが自然なのだと実感した。
例外もあるが、それは稀なケース
もちろん、中には職場で真の友情を築いているような人もいる。
またそれが異性の場合、友情を超え、結婚にまで至る人もいる。私の勤務先にも職場結婚した人はそれなりにいる。しかし、私自身にはそのような縁はなかった。
おそらくASDやADHDの傾向がある私には、そもそも職場の人間関係の構築が難しかったこともあるのだと思う。
私なりの結論 ― 職場に「友情」を求めない
友達が欲しいなら、職場の外で探すべき
会社という場で、友情関係を築くのは非常に難しい。所詮は業務上の人間関係にすぎず、それ以上でもそれ以下でもない。
やや冷めているように見えるかもしれないが、「職場に友情を求めない」というのが私のスタンスである。
職場は、生活費を稼ぐために働く場所であり、友達を作る場所ではない。もし友人関係を築きたいのなら、趣味やコミュニティなど、上下関係や業務上の利害のない、職場以外の場で築くほうが望ましい。
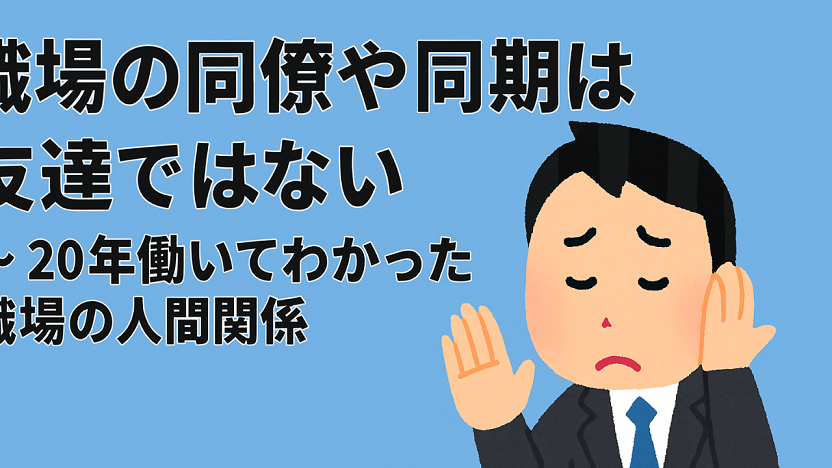
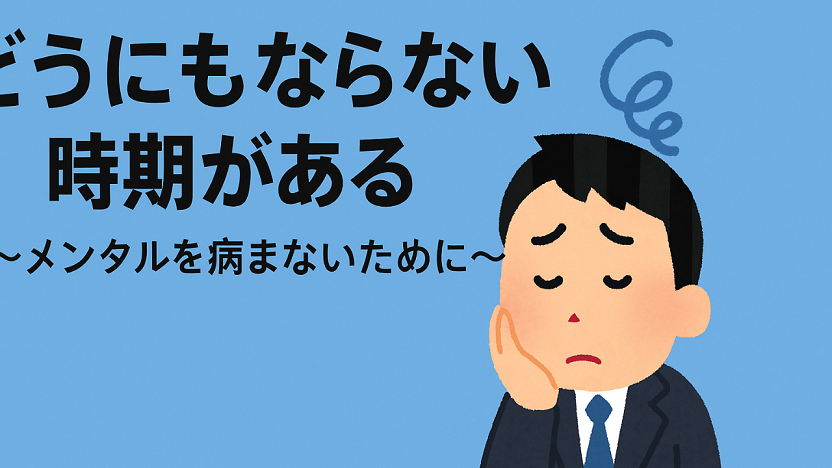
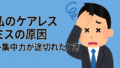
コメント