職場にいるだけでストレスが溜まる
ASD・ADHD傾向のある私にとって、職場にいるだけでストレスが溜まるのが現実である。
- ミスや失言で責められる
- 頑張っても評価されない
- やりたいことを任せてもらえない
このような日々が続けば、嫌でも負の感情が湧いてくる。前向きに考えようとは努めているが、感情の切り替えはそう簡単にできるものではない。
だからこそ私は、職場の外でストレスを解消することを強く意識している。
なお、ここで紹介する方法は、出世や昇進を目指す人にとっては参考にしない方が良いと思う。
むしろ、職場との距離をとる方法であり、ネガティブな内容を含むため「こういう考え方もある」といった程度で読んでいただけるとありがたい。
① とにかく早く帰る。職場にいないことが最大のストレス解消
私は職場にいるだけでストレスが増えるので、まずやるべきは「会社にいる時間を減らすこと」である。そこで私は次のようなマイルールを決めている
- 残業は極力行わない
- 土日は可能な限り出勤しない(やむを得ず出た場合は、残業代ではなく代休を取得)
- 週に一度は「何があっても定時退社」と決め、その時間を趣味や家族に費やす
このように意識して行動するだけで、心の余裕は格段に変わってくる。
② 運動で頭を空っぽにする
一日中座ってのデスクワークは、思考ばかりが疲弊し、逆に集中力の低下やミスの増加を招く。
特に私は庶務やマルチタスクが苦手であるため、周囲からは「大して働いていない」と見えても、定時には頭がヘトヘトになっていることが多い。
そこで取り入れているのがジョギングである。
週に一度は、自らをしっかりと追い込む運動を行っている。激しい運動をしている最中は、余計なことを考える余裕がなくなり、結果として思考がリセットされる。
息が上がって苦しいが、職場での嫌なことを完全に忘れられる。この「頭のリセット」こそが、私にとっては大きなストレス解消になっている。
③ 「職場と無関係な人間関係」をつくる
趣味や語学など、職場とは一切関係のない人間関係を築くことは、精神的な安定を得る上で、大事だと思う。
勤務時間外であっても職場の人間と接していれば、役職や立場などを意識せざるを得ず、心からリラックスすることは難しい。だが、職場と無関係なつながりであれば、しがらみもなく人間付き合いができる。
例えば、同じ趣味を持つ友人なら、ただ純粋にその話題で盛り上がれる。たとえ職場では評価されなくても、趣味の世界では認めてくれる人がいる。
そんないわゆる「第3の居場所」があると、逃げ場になり救われる感覚がある。
社会人になってから新たな友人を作るのは難しいと感じがちだが、地域のコミュニティやオンライン上のコミュニティを活用すれば、少人数でも良質な関係を作れる場があると思う。
そこでは意外と気の合う人が見つかるものだと思う。
やらない方がいいストレス解消法
私が推奨しないストレス解消法もある。
- 親しい職場の人と飲みに行って愚痴をこぼすこと
- 気分転換と思い職場のイベントや飲み会に参加すること
親しい職場の人間と飲みに行って愚痴を言うのは、相手も同じ職場の人間なのでこちらの状況を容易に理解してくれ、その場ではスッキリするかもしれない。
だが、調子に乗って言い過ぎた場合、翌日になって自己嫌悪に陥ることが多い。
また、職場の飲み会は、活躍している人間にとっては肯定される場となるかもしれないが、私のような「ダメリーマン」にとっては、会話に入れない、無視される、場合によっては日々の業務や態度について説教されるリスクすらある。
さらに、職場の飲み会では「空気を読む力」や「根回し」といった、ASD・ADHD傾向の人間が苦手とする能力が求められる。参加することで、気分転換どころか、むしろストレスが増す可能性が高い。
もちろん、こうしたイベントを断ることにより、職場内での印象にマイナスがつく恐れもある。したがって、あくまでも自己責任の選択として判断する必要がある。
特に、私が勤めるような電力会社のような日本的企業文化では、「業務能力」以上に「人付き合い」が評価基準になっている節があると思う。
まとめ──「逃げ場」があるから、明日も会社に行ける
負け惜しみに聞こえるかもしれないが、私は「仕事がすべて」だとは思っていない。
職場で働く限り、ストレスは避けられない。だからこそ、自分なりの逃げ場やリセットの時間を持つことが、精神を安定させるために欠かせない。
- 早く帰って、自分の時間を確保する
- 運動によって余計な思考を排除する
- 職場と無関係な人間関係を築く
これらが私にとってはメンタルを正常に保つ根源になっている。
私の体験が少しでも参考になれば幸いである。
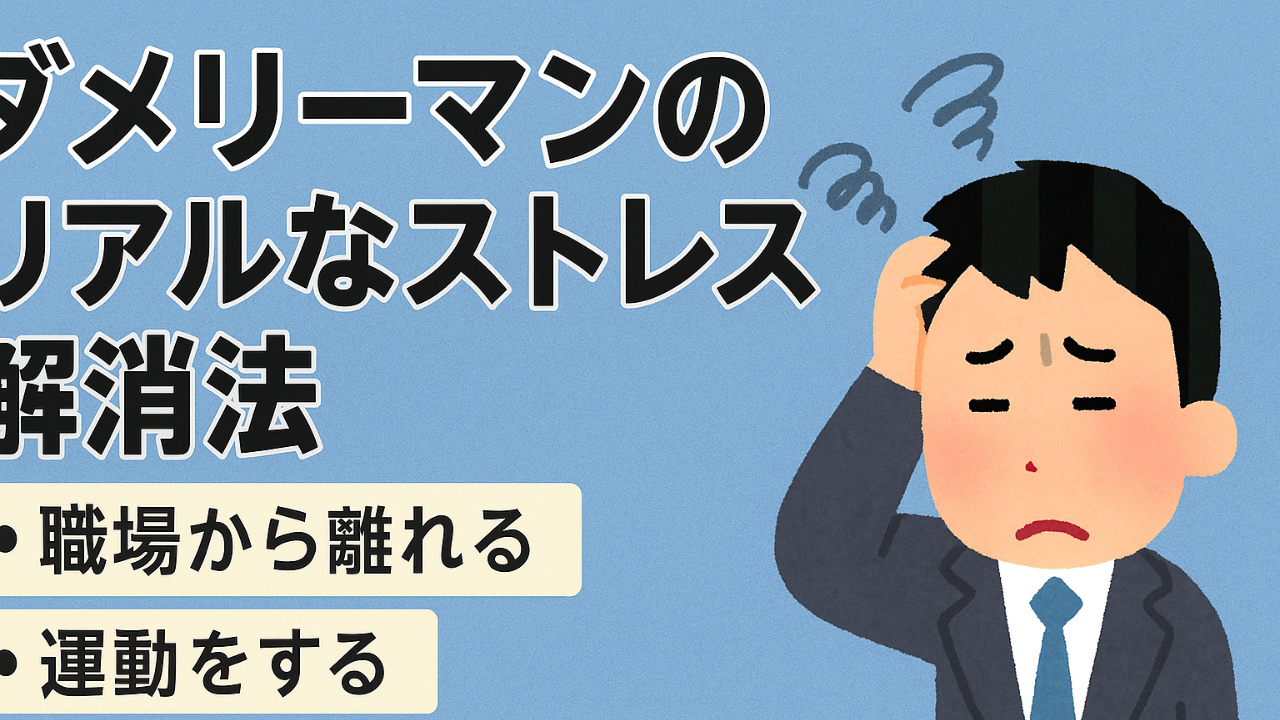
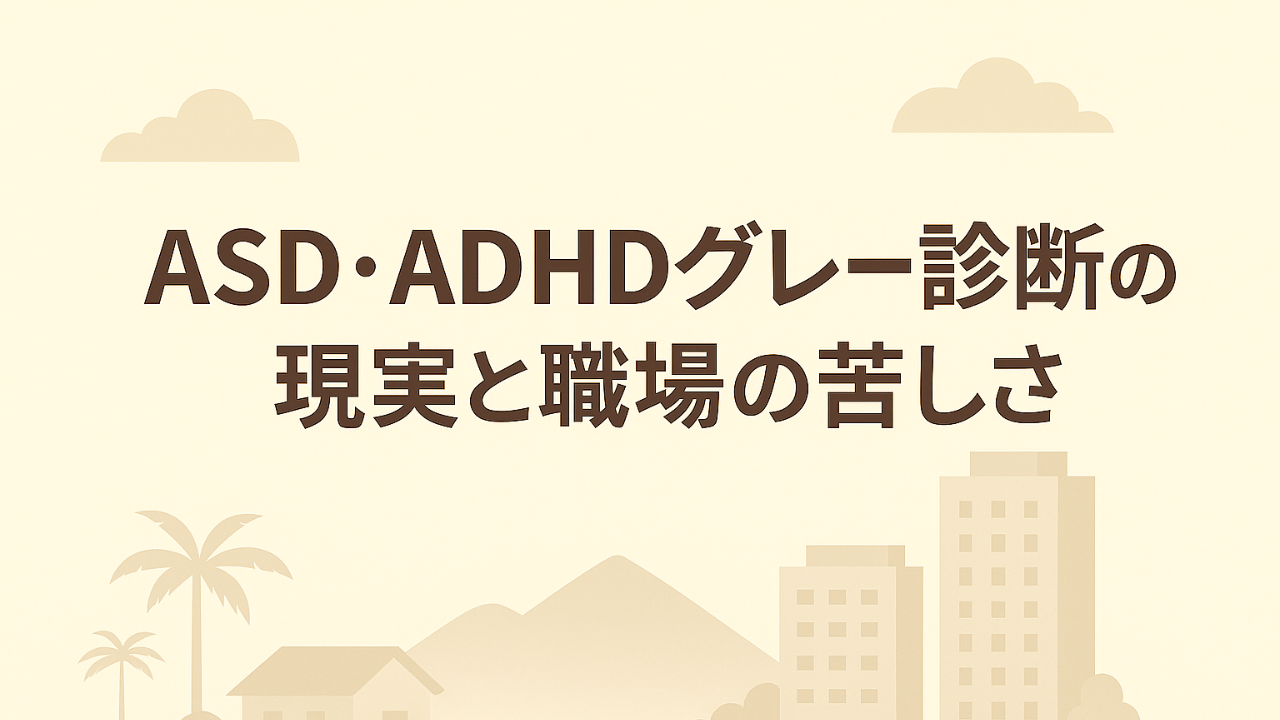
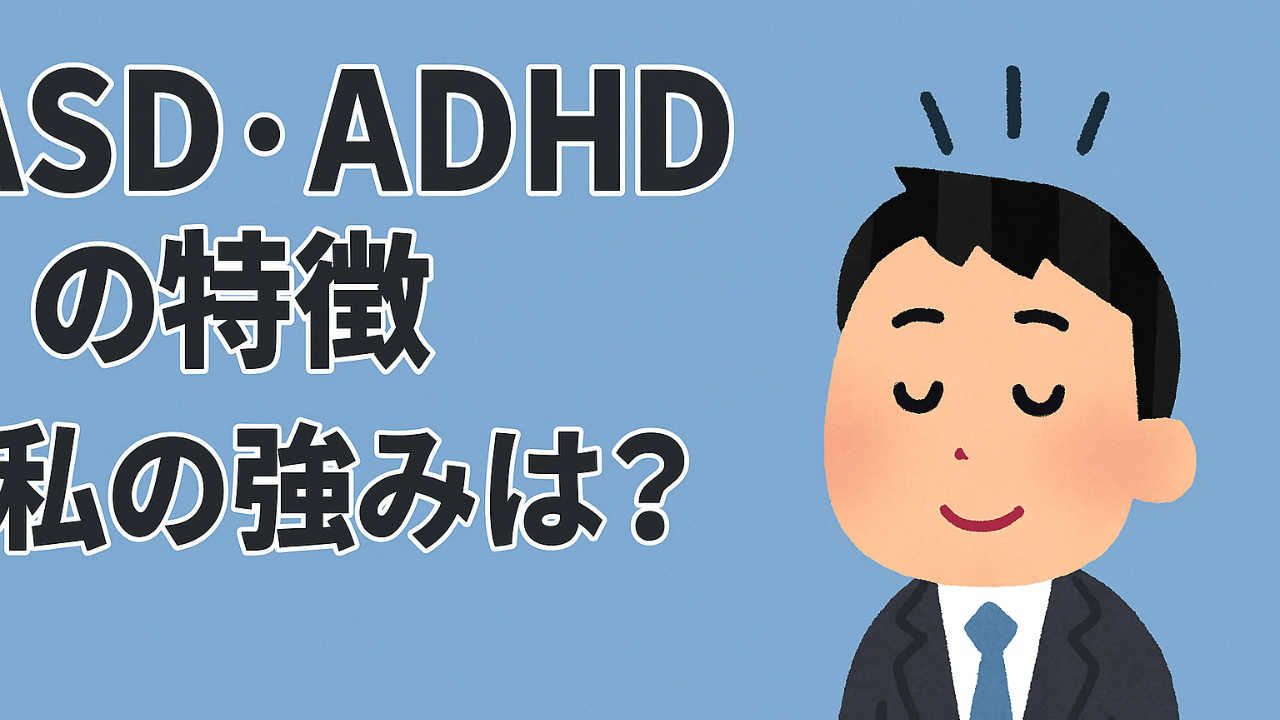
コメント