最近、ヤフーニュースで「新入社員は成果主義より年功序列に回帰」という記事を目にした。内容は2025年度の新入社員は成果主義よりも年功序列や終身雇用を志向しており、安定志向が強まっているという内容であった。
はじめは「今の若い人たちがそんなに安定を求めるのか?」と意外に感じたが、長期的な安定雇用や着実に上がる給与を望む人も多いのだと思った。実際、会社員として働くことを選ぶ人の多くは、安定した生活基盤を求めているのだと思う。
この記事を読んで、私は自分自身が就職活動をしていた「就職氷河期世代」の頃を思い出してしまった。成果主義という言葉はこのころから流行りだした言葉であり、多くの企業が年功序列から成果主義の導入を検討していた時期だと思う。そこで今回は、これまでの私の体験を交えながら「成果主義」について改めて考えてみたい。
氷河期世代が直面した就職環境
私が大学を卒業したころはいわゆる「就職氷河期」であった。バブル崩壊後の不況により、企業は新規採用を大幅に絞り込み、就職活動は極めて厳しい状況であった。
とにかくどこの企業も公務員も採用人数が少なく、学生側は少ない採用枠をめぐって必死にならざるを得なかった。圧迫面接や理不尽な選考が横行し、入社しても長時間労働やサービス残業は当たり前の時代であったと思う。またパワハラという言葉もまだ一般的ではなく、上司の言うことに従わなければ職場に居場所がなくなるような雰囲気であった。サービス残業も当たり前に行われていた時代であったと思う。
私が入社した電力会社は幸い圧迫面接はなかったが、それでも入社後は今でいうパワハラやサービス残業は当たり前にあったと思う。実際、10年ほど前までは「一定時間以上の残業代を請求しないのが普通」といった空気がまだ残っていた。
そんな時代背景の中で流行りだしたのが「成果主義」であったと思う。
政治と社会が後押しした成果主義
2000年代初頭、小泉純一郎内閣と竹中平蔵氏による改革が始まった時であった。郵政民営化や派遣法の緩和、公務員削減など「人件費削減」を推進する政策が相次いだと記憶している。世間もこれを支持し、「公務員は高給取りなのに働かない」「楽して稼いでいる」という風潮が強かったことも覚えている。
その流れに合わせて、企業も「能力主義」「自己責任」といった言葉を掲げ、成果主義は「頑張った人が報われる公平な制度」と推進していたと思う。しかし実際には人件費削減の口実として利用された側面が大きかったのではないだろうか。
経団連も「人件費=コスト」という考え方を強調しており、社員をいかに安く効率的に働かせるかが経営のテーマになっていたように思う。
当時、バブル世代の中には「年功序列では報われないから成果主義の方がよい」と考える人も一定数いたのだろう。しかし氷河期世代の私からすると、成果主義はどうしても「使い捨て」「不安定」のイメージが強く、むしろ安定した公務員を第一志望にしていたほどである。
そもそも成果主義とは何か
前置きが長くなったが、そもそも成果主義とは何なのか改めて考えてみた。
営業の売上や契約件数など、数値で明確に表せる業務なら成果主義は分かりやすい。しかし、会社の仕事の多くは数値化することが難しい。例えば庶務、設備の点検・保守、安全管理などは「問題が起きないこと」自体が成果であると思う。
電車やバスの運転手も同じだ。事故を起こさず、安全に乗客を目的地まで運ぶことが最大の成果である。しかし「当たり前」では評価されず、運転手が給料削減やリストラの対象にされたといったニュースも耳にしたと思う。
さらに成果主義は評価基準が曖昧であると思う。実際のところ、上司の好き嫌いや裁量に左右される部分が大きいのではないだろうか。私自身、残業時間を正しく勤怠表に反映させようとした際、上司にひどく嫌がられた経験がある。
結局「上に従順で、文句を言わず長時間働き、残業しても請求しない人」が評価されていたのだと思う。
成果主義とは名ばかりで、実態は「安く長時間働かせるための仕組み」に過ぎなかったのではないか。
成果主義がもたらす疲労
成果主義にはもう一つ大きな問題があると思う。それは「成果を出し続けなければならない」というプレッシャーである。
若いうちは体力もあり、多少の無理も利く。しかし40代を過ぎれば体力は確実に落ち、若い時のように常に高い成果を維持し続けるのは難しい。成果主義の下で働く人の中には、疲弊し、燃え尽きてしまう人も少なくなかっただろう。
これはプロのスポーツ選手に似ている。彼らも20代は第一線で活躍できるが、30代後半から40代で引退する。人間の限界は明確にあるのだ。
今の若い世代は情報を多く持ち、我々氷河期世代の体験談も耳にしているのだと思う。そのため「成果主義の負の面」も理解しており、安定志向を選んでいるのだろう。
まとめ
氷河期世代の私にとって、成果主義には良い印象がない。
その理由は以下の3点に尽きる。
- 人件費削減の口実として使われたこと
- 評価基準が曖昧で、上司の好き嫌いに左右されやすかったこと
- 成果を出し続けることが困難で、人を疲弊させたこと
成果主義は一見「公平」や「能力主義」に見えるが、実際はそうではなく、むしろ従業員を安く使いたおす仕組みとして利用されてきたと感じる。
だからこそ、今の若い世代が年功序列や終身雇用を望むのも理解できる。本当に公平な評価が行われ、頑張った分、給料が上がるならば成果主義も悪くないと思うが、現状では都合よく従業員を使いたい制度にしか見えてこない。
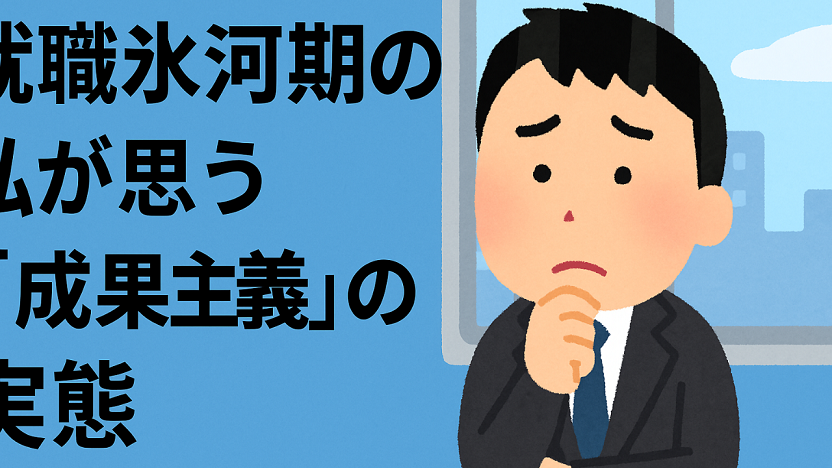


コメント