① 子どもの頃からの違和感
私は小さい頃から、言葉をスムーズに話し始めることができない特性があった。いわゆる「どもり」「吃音」だ。
小学校や中学校の国語の授業では、教科書の朗読に当たるのが嫌だった。
先生から当てられないようにと祈っていたものだ。
高校生になる頃には少し落ち着いてきたように感じたが、完全に治ったわけではなかった。
そして、40歳を過ぎた頃から再び吃音が目立つようになり、ここ数年は特にひどくなってきた実感がある。
② 私の吃音の特徴と変化
私の吃音は、主に「連発(あ、あ、あの……)」と「難発(言葉が詰まって出てこない)」の2つのタイプが混在している。とくに困っているのは難発で、頭の中では言いたいことがはっきりしているのに、口から言葉が出てこないのだ。
これまでは無意識のうちに、言いにくい言葉を避けたり、言い換えたりしてきたのだと思う。
そのため、聞き手からは話が回りくどいと感じられていたかもしれない。
ある程度は言い換えが可能な言葉ならなんとかなる。しかし、人の名前のように言い換えがきかないものは、どうしても詰まってしまうことがある。
③ 日常で困る場面と誤解
吃音による困りごとは、日常のささいな場面にも影響する。たとえば、電話でお弁当を注文するような簡単な業務であっても、言葉が詰まることがある。弁当名は言い換えが利かないため、詰まってしまうと、どうしようもなくなる。
以前、役所から職場に電話があり、上司の名前を尋ねられた際に詰まって沈黙してしまったことがあった。その上司の名前は、私にとって特に発しづらい音で始まる名前だった。おそらく相手は「この人、本当に上司の名前も知らないのか?」とあきれたに違いないと感じた。
また、庶務などの業務では、不特定多数の人と電話でやり取りをすることが多く、人の名前を聞かれる機会が多々ある。
吃音のためにスムーズに対応できないと、相手に「変な人」「自信がない」「ごまかしているのでは」と誤解されてしまうのではないかと、不安になる。
④ 真似される苦しさ、気づかれにくい悩み
吃音の「連発」については、見た目にもわかりやすいからか、以前、新入社員だった頃に同僚から話し方を真似されて笑われたことがある。とても嫌な思い出である。
吃音は見た目にはわからないので、周囲からは「緊張しているだけ」「落ち着けば話せる」と思われがちだ。
また思い切って吃音の話をしても「ゆっくり話せばいい」「落ち着けばいい」と言われることがある。しかし、それで改善するわけではないので、そう言われても、正直困ってしまうのが本音だ。
自分でもなぜ普通に話せないのか原因がわからないし、「気にするな」と言われても気になる。
⑤ 話すことが億劫になってしまった今
最近では、職場で人と話すこと自体が非常に億劫になってきた。
会社員として報連相(報告・連絡・相談)が大事だということは頭では理解している。
でも、口から言葉が出ないかもしれない、また詰まるかもしれないという不安から、話すこと自体が嫌になることがある。
ASDやADHDの検査を受けたときに、吃音についても相談してみたが、「有効な解決策はない」と言われてしまった。私にとって吃音は、「受け入れて付き合うしかない現実」として存在している。
まとめ
最近、メディアなどでも吃音が取り上げられるようになり少しずつ認識されるようになってきたように感じる。
しかし、まだまだ私の周りではマイナーなのかもしれない。
私にとって吃音は、日常のあらゆる場面で不安や緊張を伴うものだ。
解決策もなく困惑しているが、私の体験が同じような悩みを抱えている誰かの気持ちを軽くする一助になればと願っている。
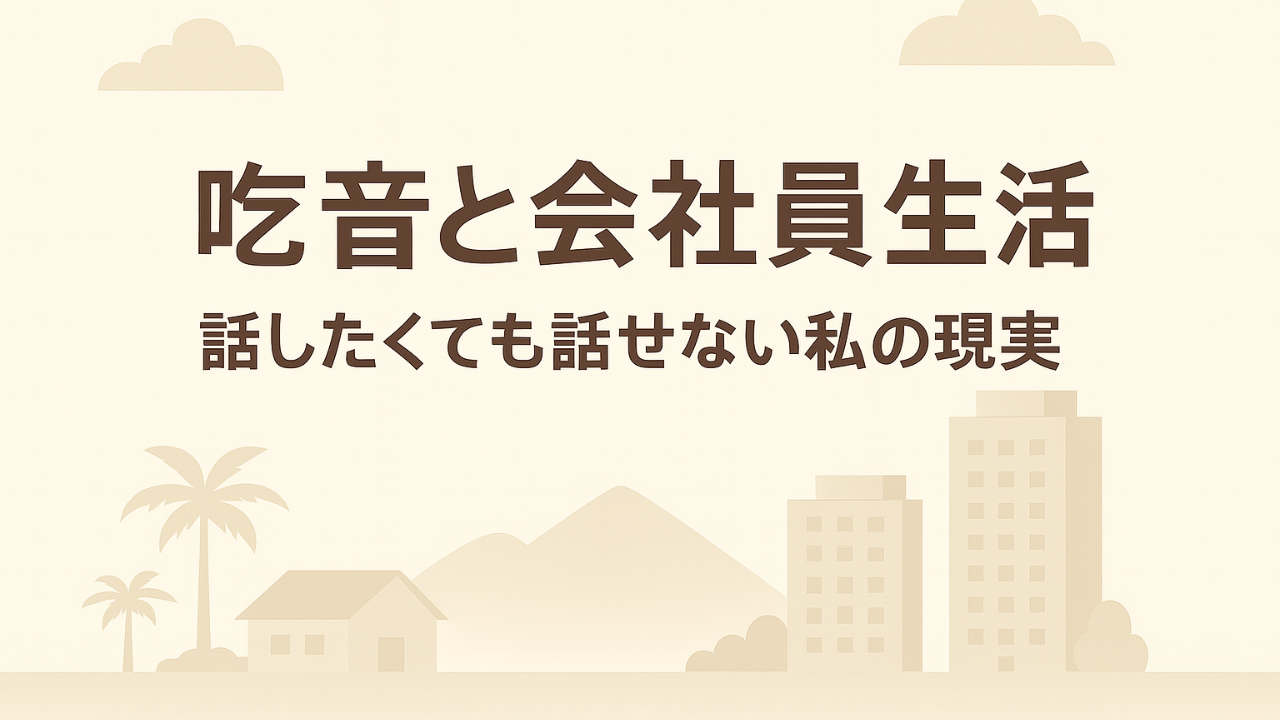
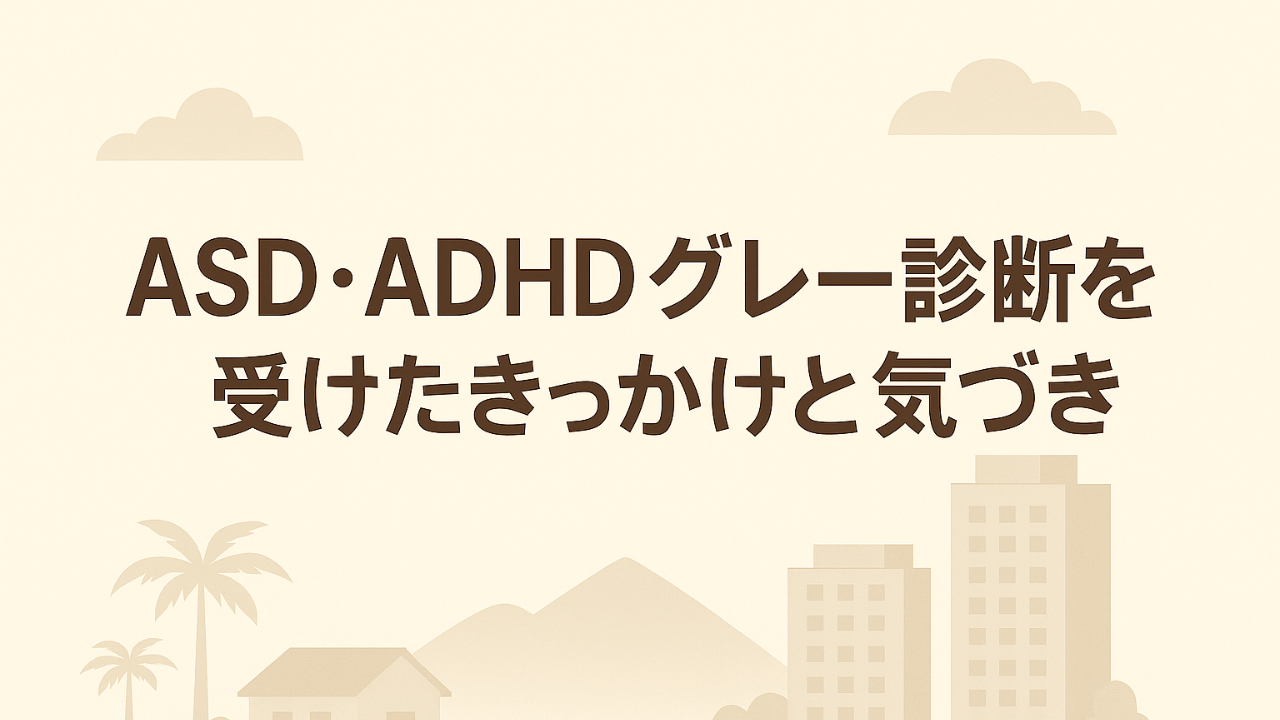
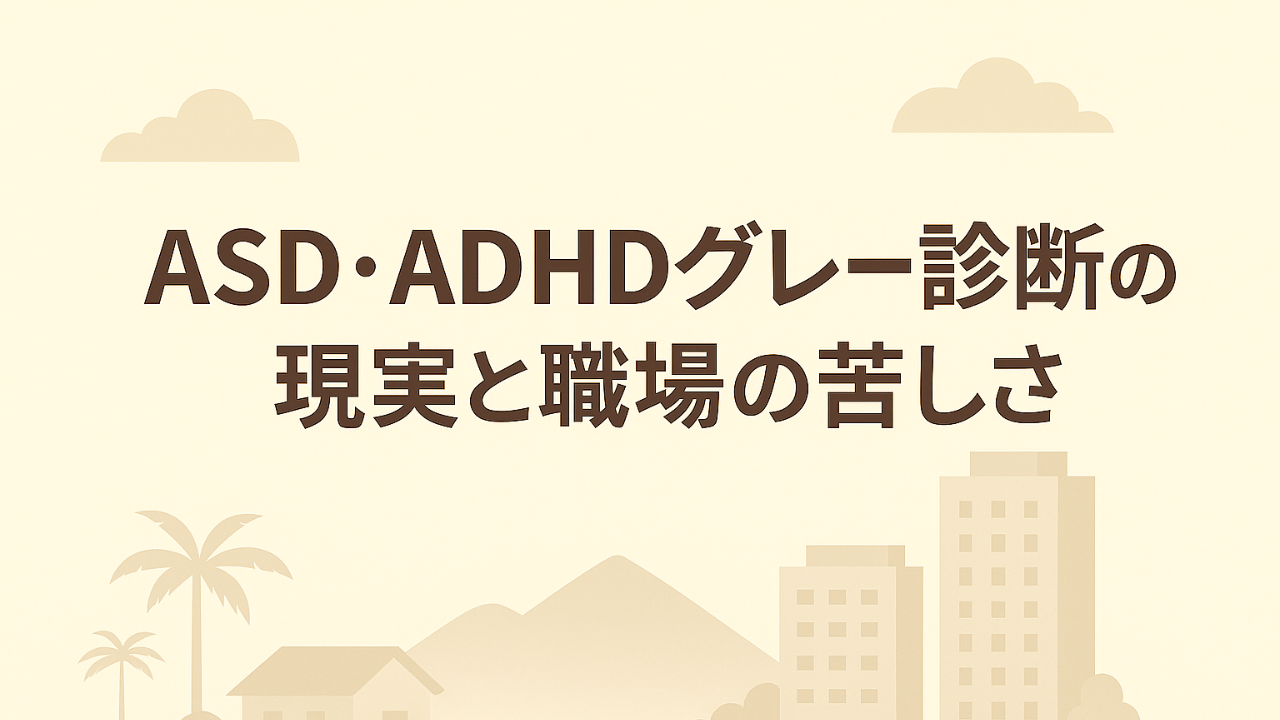
コメント