① グレー診断──はっきりしないからこそ生きづらい
私は数年前、ASD・ADHDの検査を受け、「アスペルガーの疑いあり」という診断結果を受け取った。つまり、正式な診断名がつくわけではなく、支援制度の対象にもならない 「グレーゾーン」 という立場である。
一見、普通に見える。しかし実際には、日常生活や職場で多くの困難を感じている。明確な診断が下りないことで、他人からの理解も得づらく、支援制度にもつながらない。
逆に正式な診断名が付けば、障害者手帳の入手や合理的配慮などの支援を受けられたのだと思う。
グレーという中途半端な結果であるため、「ちょっと変わってる人」「協調性がない人」といった、曖昧なレッテルだけが先行してしまうのが実情だ。
② 自分を振り返って気づいたこと──特性の数々
検査を通して、自分の特性について深く考えるようになった。思い返せば、昔から「ちょっと変わってる」「話が飛ぶ」と言われることが多かった。
- 一つのことに強く集中する力はあるが、マルチタスクや段取りを求められる庶務は極端に苦手
- 集中している最中に話しかけられると、極端に疲れやすい
- 集中力が切れると、ケアレスミスを連発してしまう
- 「いつも焦っている」「落ち着きがない」と言われる
- 人の話をちゃんと聞いていないように見られる
- ズボンのチャックや洋服のボタンの閉め忘れなど、細かい抜け漏れが多い
- 誤字脱字に気づけないことが多く、文章の完成度が低い
運動面では、球技や体操などの器用さを求められるスポーツが苦手だ。
健常な人なら自然にできるであろうボール投げも、私にはうまくできない。スキップもできるようになるまでかなり時間がかかった。(動きはぎこちない)
だがその反面、長距離走や水泳など、一人で淡々と進めるスポーツは得意だった。こうした特性は、典型的なASD・ADHDの傾向とかなり一致していると自分でも思う。
③ 今の職場とのズレ──特性を活かせない環境
今の職場では、取りまとめ役や庶務業務を割り当てられることが多い。だが、これらの業務こそが、私にとって最も苦手な領域である。
私の職場では「庶務がちゃんとできない人には、専門的な仕事は任せられない」という暗黙のルールがあるようだ。
だが、庶務こそ「誰でもできる」仕事ではないと私は思う。
臨機応変な対応、細かな確認作業、高度な調整能力が求められる。
私にとっては、それが最も苦手な部分なのである。
本来であれば、集中して取り組める業務でこそ力を発揮できるはずだが、そうした場が与えられることは少ない。
職場において、ASD・ADHDの特性を理解し、良い面も見てくれる上司と出会えることは極めて稀だと感じている。
受験にたとえるなら、5科目中4科目で80点を取っても、1科目で30点を取れば不合格。そんな評価のされ方に似ていると感じる。
④ 「誰でもできる仕事」が一番つらい──私の働きづらさ
世の中では「コンビニの仕事は誰でもできる」といった声もある。だが私にとっては、コンビニ業務のようなマルチタスクと臨機応変な接客対応が求められる仕事は難しいと思っている。
「普通の人ができることができないのはダメ」とか「基本的なことができないとダメ」という評価軸がある限り、ASD・ADHDの特性を持つ人間は、「ポンコツ」や「要領の悪い人」と見られてしまうに感じる。
そもそも「普通って何だろう?」と、自分でも考えてしまうことがある。
私自身、「もう少し丁寧にやれば」「ちょっと気をつければ」といったアドバイスを何度も受けてきた。しかし、その「ちょっと」が難しいのだ。
⑤ まとめ──欠けている部分ではなく、特性を見てほしい
ASD・ADHDの特性を活かし、大きな成果をあげている人たちが世の中には多くいる。
だが、そうした人たちは「適切な環境」や「理解のある上司」に恵まれている場合がほとんどだと思う。
言い訳っぽく聞こえるかもしれないが「足りない部分」ばかりが評価される環境では、強みを発揮する機会そのものが与えられない。
マイナスの部分を多く書いたがASD・ADHDの強みもあると感じている。私もまた、自分の苦手さを受け止めながら、強みに目を向けていきたい。
同じ苦しさを抱えている誰かの心を少しでも軽くできたらと思う。
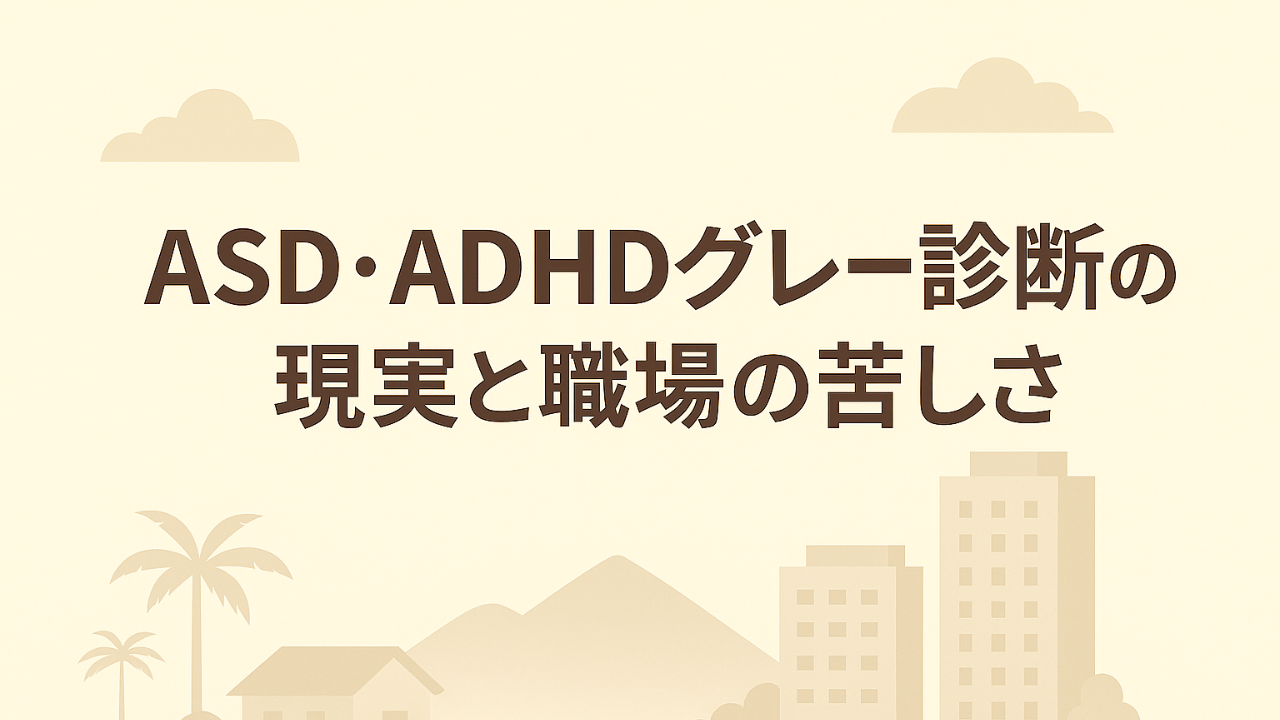
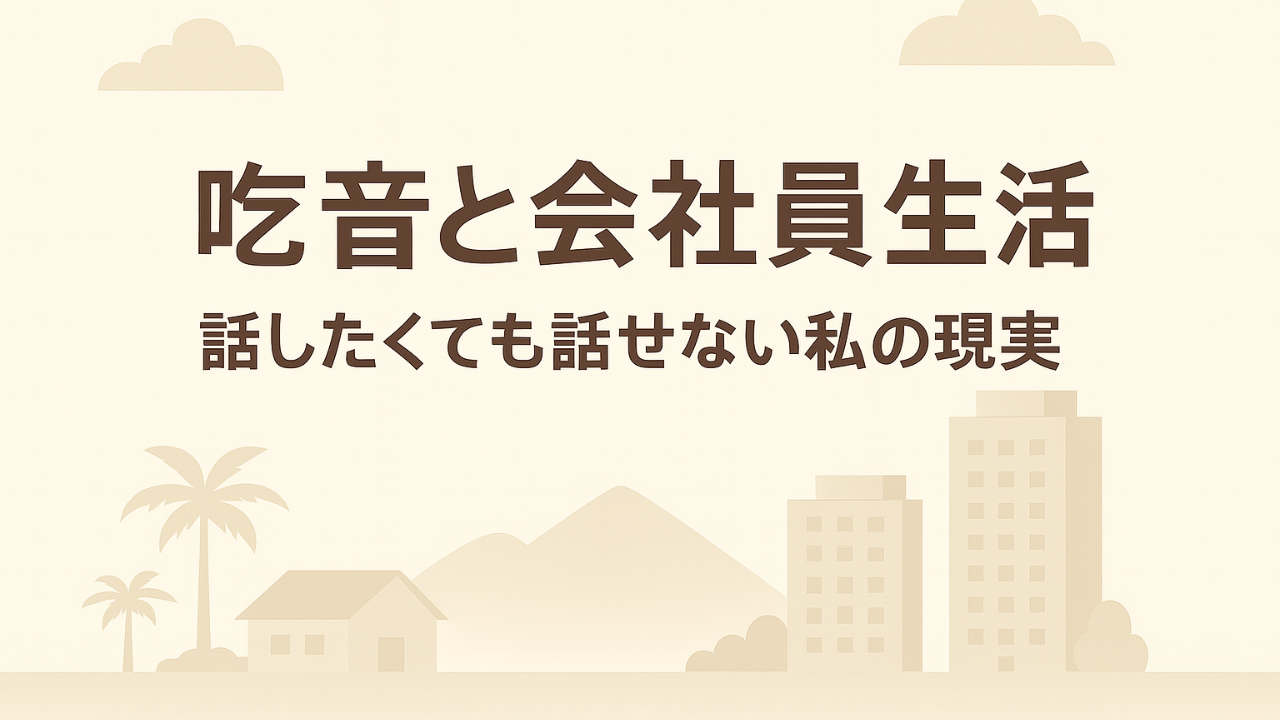

コメント